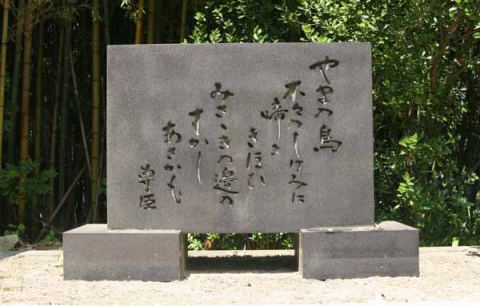| 7 �����@�L�����@���莛�@�������@�V�����@�����哰�@�V���@���z���@��˖�_�������@�h�ю��@�_���@���R���@�Ε����@�ב����@����@�@��y���@ ��掛�@���|���@���ю��@�~�����@�i���@�ԎR�@�@�������@�L�ˎ��@ �ϐ����@ �ӏ����@�������@�������@�������@�V�㎛�@ �\�����@�^�����@�@�@���@�{�����@�������@���R���@���r�_�@�_������{�v����{�����@ |
7 ���ɂ̕��t
�����@�@
���s
���@�@
�L�ώ�
���̃y�[�W�̖ڎ���
�ߏ��卶�q�傪��Ɗ������s����
���@�ŁA�ߏ��̕�(���w��j��)������
�L�ώ��͑T�@�̎��@�ł��������A��k�����㌳�O�R�N(1333)�ɐ����A�p���ƂȂ����B�]�ˎ���A
�����S�N(1714)�ɓ��@�@������l(1667-1738)���ċ������B�ߏ��卶�q��͂��̍ċ��ɋ��͂�����l�ł���B
�ߏ��͔ӔN�̏\���N�Ԃ����ō�Ɗ������s���A1724�N��72�Ő��U���I�����B
 �@
�@
���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�R��Ǝj�Ջߏ��卶�q��揊�W

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�R��̝G�z�u�@�ӎ�@�v�i������l�j
 �@
�@
���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�萅��

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�{���@�{���̉E�ɋߏ��̕悪����B
 �@
�@
���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�{���@�E�ʐ^�͎R�卶�́u�ߏ��卶�q��揊�����ȁv�̔�

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@������ׂ̒���

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@������

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�������̝G�z�u�������F�v
 �@
�@
���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@����ƎR��i�����j

���s���@�@�L�ώ��ɂāi8���j�@�ߏ��卶�q��̕�i���̎j�Ձj
�ʐ^�N���b�N�f��D�g��
 �@
�@
���s�ߏ������ɂāi8���j�@�L�ώ����̌����ɂ����ߏ��卶�q�哺���@�E�ʐ^�͋ߏ��L�O��
����
�쐼�s
����R�^���@
���莛
���̃y�[�W�̖ڎ���
�p���ʎ߂ő��c�@�̐m����Ⴂ���m����
���a�����̋F�菊�A�����ۓ`���A��c�����̕�̂���1200�N�̌Ù�
�_�T�N��(724�`728)�����V�c�̖��ɂ�菔���ɖ��莛����������������l���A�ےÍ��̖��莛�Ƃ��Đ��ω���
�{�����J����B����Ɉ��a���N�i968�j�ےÂ̍����c�i���݂̑��c�_�Ђł��鑽�c�@�j�ɖ{���ɍ\�������a����
�̑c��������A���̎��ɐ[���A�˂��A��㌹���ꑰ�̋F�菊�Ƃ��Đ��h���W�ߔ��W�����B

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�m����
����21�N�Ɍ��݂��ꂽ�������m����@�m���͑��c�_�Ђɂ���������
�p���ʎߗ߂ɂ�葽�c�@�͑��c�_�ЂƂ��Đ����c�������m���͖��莛�Ɉڂ��ꂽ
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����@�@�E�͐m����O�Q��
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�R����m���i�����c�@�@�����c�_�Ђɂ��������p���ʎ߂ňڂ��Ă����j
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�Q���@���ʐ^�͐m���傩��������ʁi����j�@�E�ʐ^�͂��̋t�i���j

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����O�Q��
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�m������ʎQ���@�E�ɍ��̉�

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����O�Βi

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����
���{���͐����ϐ�����F
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@���O�Ǝ萅

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@����
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����哰�@�@�O�@��t��
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�ω����@�@�E�͝G�z
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�����{�@�@��ב喾�_
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�s�������@�@�q���n����
 |
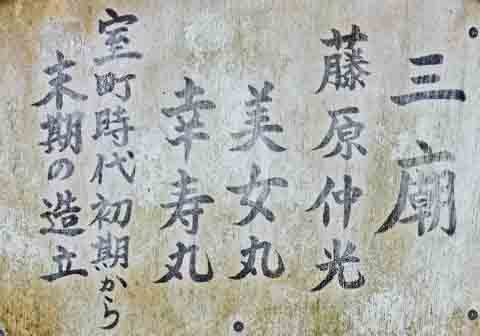 �����ۂ͎�N�������̖��q�A�K���ۂ� �����ۂ̐g����ƂȂ����Ɨ����������̎q  |
�����ۂ͑f�s�������A���͔����ۂ����֗a���A�C�Ƃ��������B��������A���͏\�܍˂ɂȂ��������ۂ��Ăѐq�˂��A
�����ۂ́A�a�̂�nj��͂��Ƃ��o�����ǂ߂Ȃ������B�{���������́A�Ɨ��̓��������ɔ����ۂ̎���͂˂�
�悤�ɐ\�������B�����������́A��N�̎q�̎���͂˂邱�Ƃ��ł����A�u����g����Ɂv�Ɩ��������o���䂪�q
�K���ۂ̎��f���̎v���Ŗ����ɍ����o���A�����ۂ��Ђ����ɓ��������B��ɂ����m���������ۂ�
�������߂Ĕ�b�R�ŏC�s�ɗ�݁A�₪�Č�����苗��i�������j�Ƃ������m�ɂȂ����B

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@�_�G�R���莛�@�����O�Γ�

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@����R�^���@�_�G�R���莛�@���Ƃ̎��� �ʐ^�N���b�N�Ŏ����̑���

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ���莛�@��c�����̕�
�������̉Ɨ���c�����i�����Y�j�̕�
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�l�����\���J������߂���@�@�E�͑��ԗ���R��

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�i���~�o�@�j
 �@
�@ 
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V

�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�뉀
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@�{�V�뉀
 �@
�@
�쐼�s���莛���ɂāi7���j�@ ����R�^���@�_�G�R���莛�@���W
���ʐ^�́u���r�c���E���R���v�@�E�ʐ^�́u���c�_�Ёˁv���w��
���莛���͐쐼�s����n�ł���A���͕͂�ˎs�ł���B
�@�@
�����쒬
��y�@
����R������
���̃y�[�W�̖ڎ���
�s���l���J��Ƃ����Ù�
�؋���l�����삵��14��̖؋����u
�O�}�{���Q�q���ꂽ�c���䂩��̎��@
����������]�R�̋S�ގ��̐폟���F�肵���Ƃ����`��������A�u���̖�t����v�Ɛe���܂�Ă���B
����4�N�i1807�j�ɗV�s�m�E�؋���l��90�̔ӔN�ɗ������A���삵��14�́i�Ď�����1�̂��܂߂��15�́j��
�u�؋v�����u���Ă���B�؋���l���܍�����H��f���A�ΐH�������̎���R�A����������H�Ƃ���
�^���@�̉����ł����ؐH�̎��H�ҁB �i�����쒬�g�o�j�@�����쒬�ɂ́A�؋�������14�́A �V�����R�́A
�����哰7�̂̍��v24�̂�����B������؋��l��90�ł��̒n�ɗ����܂ɐ��삳�ꂽ�B
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�R��ƝG�z�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@  �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�R��@�E�͓������@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�{���@�{���͈���ɔ@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@��t���@�{���͖�t�@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��
��t���ɂ͖�t�O���̉��ɖ؋�14��i��2��͊O���W����֑ݏo���j�����u����Ă���B�O�ɂ͕o��ḑ��ґ��i���[�ʐ^�j
�E�[�̎ʐ^�͖؋���l�ɂ�鎩�����i���c�Z�E�����B�e�֎~�̂��������쒬�g�o���j�@�@�e�n�̖؋��̎ʐ^
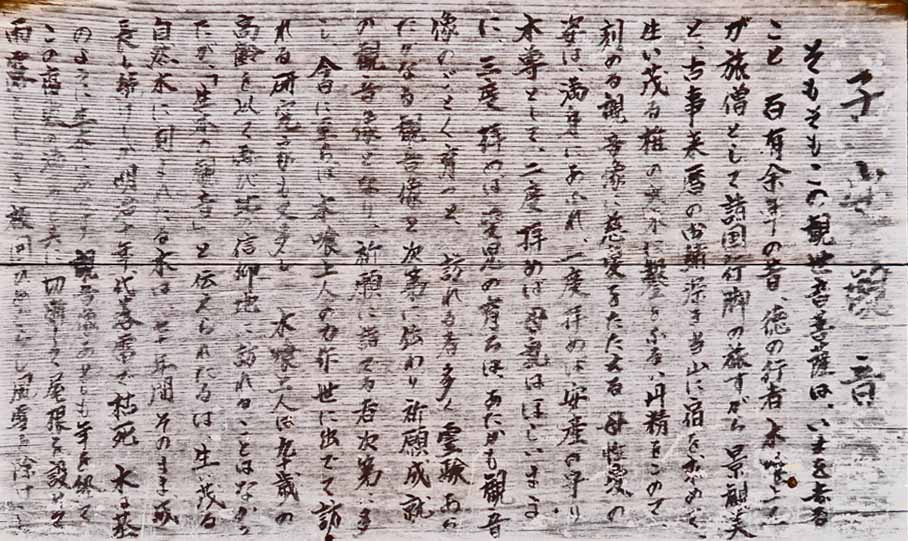 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�q���ω��@�@�@�N���b�N�Ŋg��
�E�[�̎ʐ^�͖؋���l���X�O�Ő��삵���Ƃ����؋��i�����B�e�֎~�̂��������쒬�g�o���j

���������@�؋���l�̏\�������@�Y�o�V���@H29.9.20�@�������
�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@���O�@�E�͌ɗ��@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@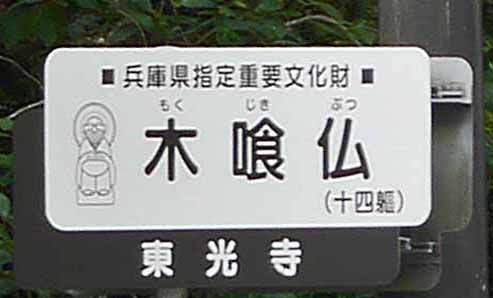
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@����R�������@�Δ�i�O�}�{��A�̏��̔�j�@
�E�͕��Ɍ���12�����i�쐼�R���j�̓��H�W���@�@�@�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
�@�@
�����쒬
��y�@
�^�@�R�V����
���̃y�[�W�̖ڎ���
�؋���l�����삵���R��̖؋����u
�V�@�Б��_��l�ɂ��J�R�Ƃ���邪�A�Ђɂ����ďڍׂ͕s���B�V�����̖؋͎������ȂǂR��
�ł���B�؋���l�͎������𒆉��ɂ��āA����ɔ@���̘e���ł��链�吨�����F�Ɛ��ϐ������F��
����A����ɎO�������Č������ƌ����Ă���B������F���Ɗω���F����2�̂�1�{�̏��m���c����
�ɂ��Ē����Ă���̂ŁA�w�����킹�ɂ���ƃs�b�^���Ƃ������炵���B�i�����쒬�g�o�j
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@�^�@�R�V�����@�{���@�{���͈���ɔ@���@�@�@�N���b�N�Ŋg��
���Ɍ���12�����i�쐼�R���j�̓��H�W��
 �@
�@ 
���Ɍ������쒬�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�{���̈���ɔ@���@����ɎO�����@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@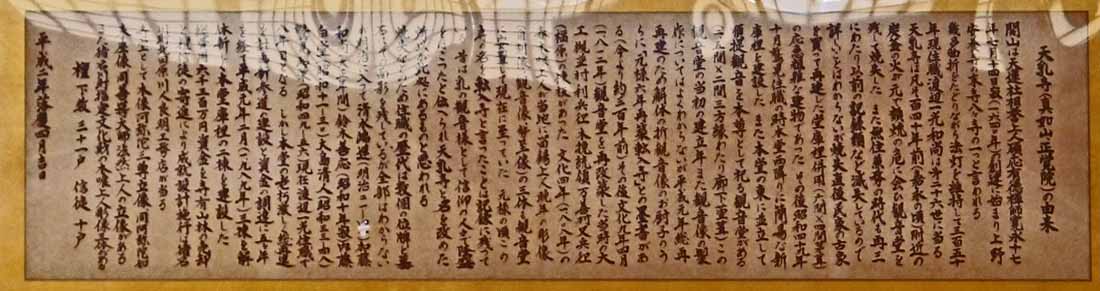
���Ɍ������쒬��y�@�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�@�{���e�Ɉ��u�̖؋R���@�@�@�N���b�N�Ŋg��
���[�ʐ^�͌ɗ��A�E�[�͖{���Ɍf����ꂽ���@�R�����z
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬��y�@�^�@�R�V�����ɂāi�X���j�@�@�{���e�Ɉ��u�̖؋R���@�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��y�@�^�@�R�V�����t�߂̕��i�@�@���ʐ^�͓��̉w���Ȃ����@�N���b�N�Ŋg��
�@�@
�����쒬
�����哰
���̃y�[�W�̖ڎ���
���R�̑n����1300�N�O���ÓV�c����ɑk��
�������q�̖���F��Ɋւ��R���[�����F�i�����D�j
�����쒬�ɂ́A�؋��l��90�ł��̒n�Ő��삳�ꂽ�Ƃ����A
�؋�������14�́A �V�����R�́A�����哰7�̂̍��v24�̂�����B
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@ �����哰�i������V�����Ɨ��e�ɖ؋�������j
���ʐ^�͔����哰���������ƉE�ʐ^�͔�����V���̍��E���e�ɖ؋R铂ÂU铁i�l�b�g����N���b�N�Ŋg���j
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@��[��������哰�̓����@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����哰�t�߂̓c�����i
 �@
�@ �@
�@���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����哰�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j �����哰�ƎQ���̈ꕔ�@�N���b�N�Ŋg��
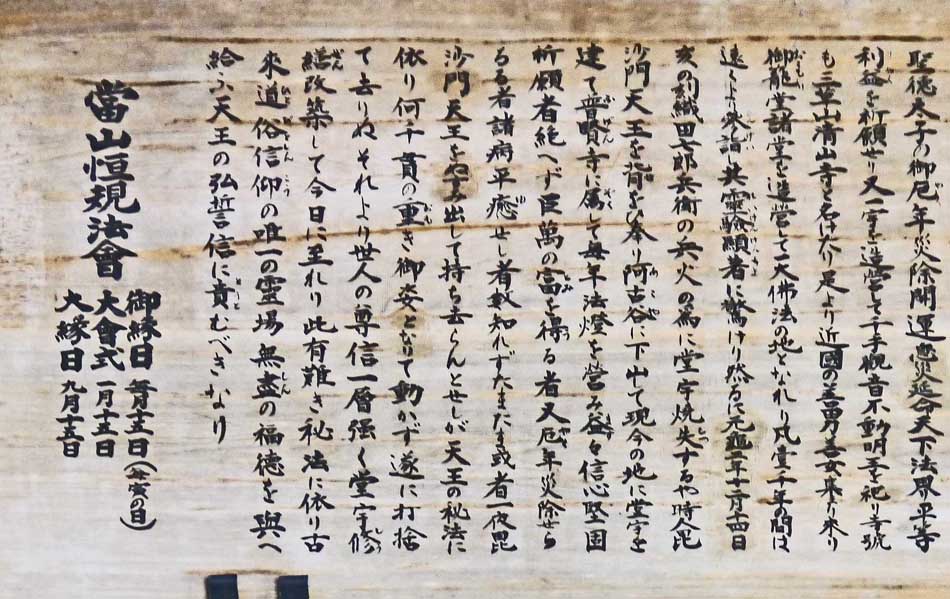
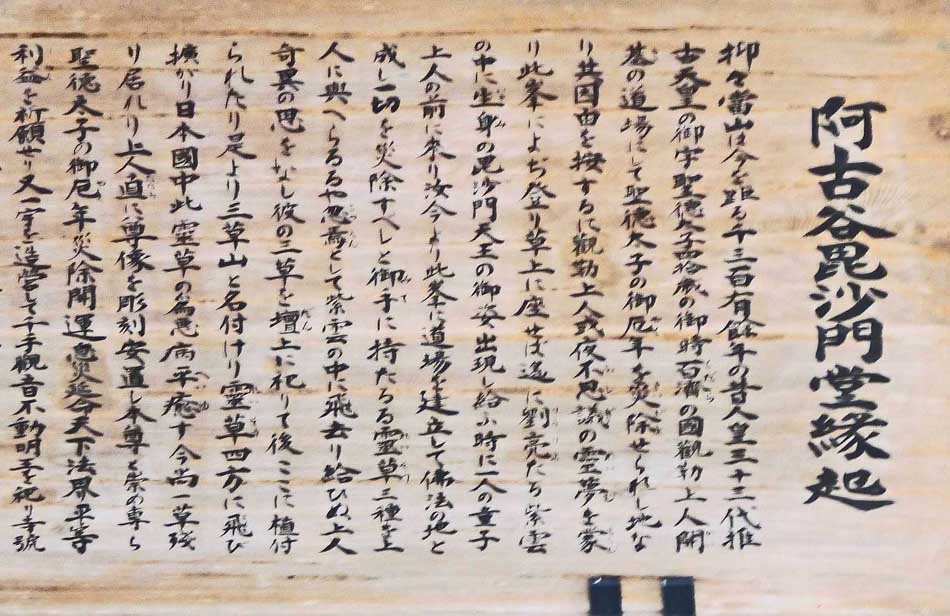
���Ɍ������쒬�ɂāi�X���j�@�����D�@�N���b�N�Ŋg��
������
�����쒬
��y�@
���_�R�V��
���̃y�[�W�̖ڎ���
�ޗǎ���ɍ��m�s��J�����A�k�É@�i��Ȃ��Â̂���j�̌�g�Ɠ`���B
�@���厛�̑啧�������ɂ������s��́A�ɒO�̍��z�����͂��߂Ƃ����l�\��@�����ĂĂ��邪�A
�k�É@�����̈�B�����̐Γ��Ăɂ͉��i10�N�i1403�j���������Ă���A���̎����̐Γ��ĂƂ��Ă�
�����ł��H�ȗ�ł��邽�ߕ��Ɍ��w�蕶�����ɂȂ��Ă���B
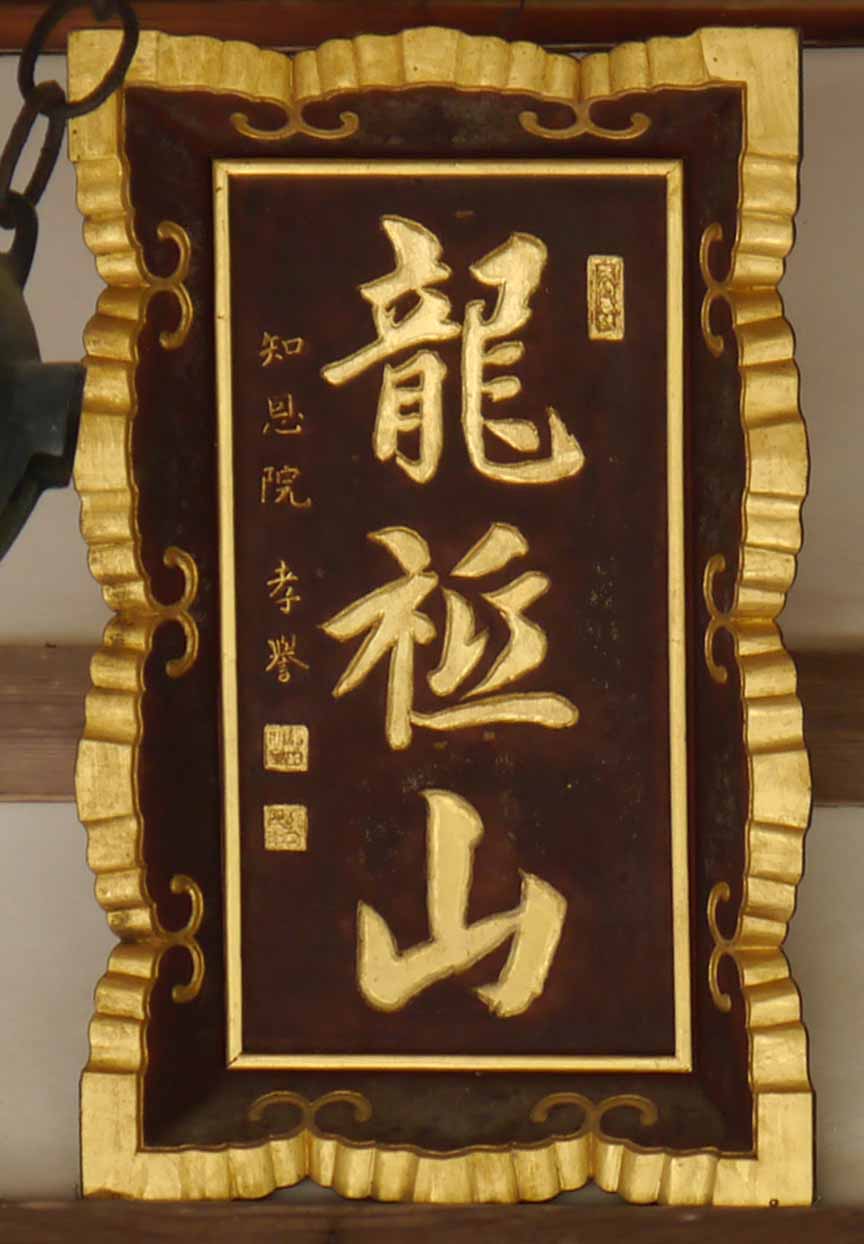 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@���_�R �V���@�{���ƝG�z�@�@���W�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@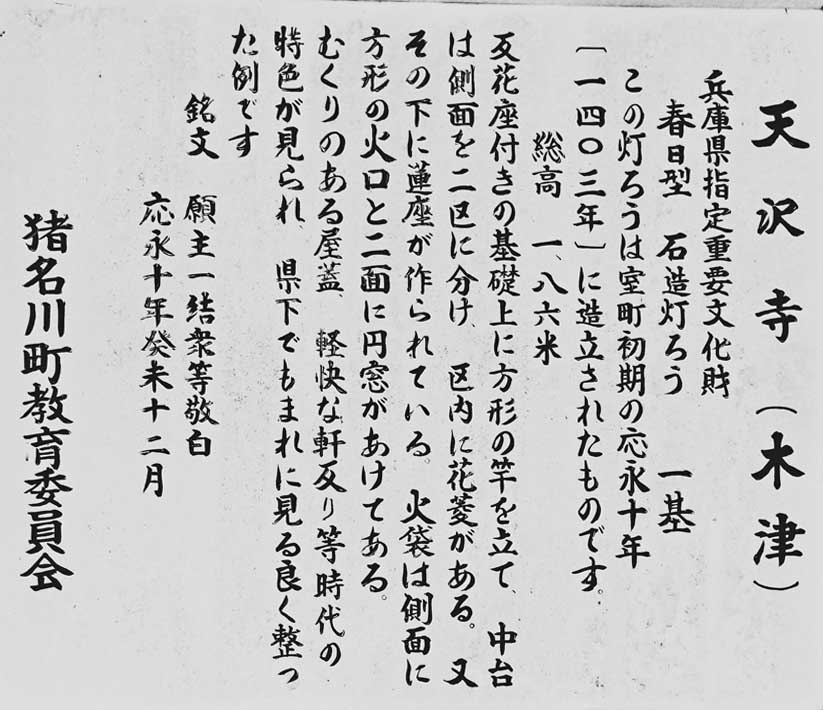
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@���_�R�V���@�{���ƝG�z�@�Γ���(�l�b�g���)�@�@�N���b�N�Ŋg��
���i10�N�i1403�j���������Ă�Γ��ẮA���Ɍ��ŋH�ȗ�ł��邽�ߕ��Ɍ��w�蕶����
�ʐ^���͓����O�\�����_�������@
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�@�V��*�@�����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�@�Q���@�@���O�@�@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�@�Q���@��O�̕����r�@�@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�����̔���_�Ё@�@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ������쒬�ɂāi�P�O���j�@�V��**�����̒n�����ق��@�@�@�N���b�N�Ŋg��
���z��
�ɒO�s
����R�^���@
���ĎR���z��
���̃y�[�W�̖ڎ���
�s������������z36�V���������ł�������
�D�c�M���ɏĂ���č]�ˎ���Ɍ���ɕ��A�����B
�����V�c�̒��菊�Ƃ��ēޗǎ���A�s����������E��49�@�̈�ŁA�V��3�N
�i731�N�j�n���̍��z�{�@�̌�g���@�B���z�R�U�V�O����ׁA�ےÑ��̋����ł������B
���̌�A�V���V�N(�P�T�V�X)�D�c�M�����L�����r�ؑ��d���U���������ɁA�{���y��
�R�U�V�͎����D���ɋA���A�]�ˎ���ɍČ����ꂽ���A�R�U�V���̑����������́A
���������o�@�A���@�A�ՏƉ@�A���A�@�̂S�@(�����n�})�����ł���B

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���R��
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�{���Ə��O

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���{���i��t�@���j
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�ω����ƒ��瓰
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�R������@�E�ʐ^�͐���
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�s��@�E�͈�ב喾�_
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�ٓV���@�E�͍s���
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���l�����\�������Ε�
 �@
�@
�ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z���R��O�@�E�͎萅��
 ���z���ɂāi�P�Q���j�@����V�c��1288�`1339�� �u������� ����̌��[�� �������� �������Ȃ�� �䂭���̋��v |
 �ɒO�s���z���ɂāi�P�Q���j�@�s�668�`749�� �u�R���́@�ق�ق�ƂȂ��@�������� �����Ƃ��v���@�ꂩ�Ƃ��v���v |
�ɒO�s
����R�^���@
�ՏƉ@
���z������
���̃y�[�W�̖ڎ���

�ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@���ĎR���z�������ՏƉ@
 �ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@�{�� |
 �ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@���� |
 �ɒO�s���z�������z�u�}�@�N���b�N�Ŋg�� �l�����i���o�@�A���@�A�ՏƉ@�A���A�@�j |
 �ɒO�s�ɂāi�P�Q���j�@����R�^���@�ՏƉ@ �ɗ� |
������
���{�s
����R�^���@�ʊi�{�R
���R������
(��˖�_)
���̃y�[�W�̖ڎ���
��˖�_�ɂ͖�J�^�̖�_�������J���Ă���B����V�c�S�P�˂�
��N�̎��A���������ƕs����������̂ƂȂ�A������Ж��ł������A
����ގ�����͂̒��Ŋ������ꂽ���ƂɗR������

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_�\��
 �@
�@
���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@���������@�E�͕s������얀��
 �@
�@
���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������ʗp����萅��

���{�s�ɂāi12���j�@�^���@���R��������˖�_�@�ʐ^�������_���A��t���A���O��
 �@
�@
���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_�뉀
 �@
�@
���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������_���@�ʐ^�E�͖�_���G�z

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�@���R��������˖�_���O��
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@��������������ɗ� |
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@��������t�� |

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R�������\��
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������@�q��n���� |
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@������������ |

���{�s�ɂāi12���j�@����R�^���@�ʊi�{�R�@���R��������˖�_��t��
 ���{�s��˖�_�������ɂāi12���j�@�뉀 |
 ���{�s��˖�_�������ɂāi12���j�@�l�����\������ |
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@������������ |
 ���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@���������O�� |

���{�s��˖�_�ɂāi12���j�@�������\����̓��k���ʒ��]
���{�s
���{�s
����R�^���@
�Z�b�R�h�ю�
���̃y�[�W�̖ڎ���
�~�a�V�c�̒��莛�@
�V���̖@����l�ɂ��J���`�����`���
�M���ɏĂ��ꂽ��A�V�ЂŔp���ƂȂ������A�ߔN�ɕ��������B
�V���̖@����l�ɂ���J��`�����`��邪�A���@�g�o�ɂ��A�~�a�V�c(786�`840)�̒���ɂ��A
�V��10�N(833)�O�@��t���J�n�����Ƃ����B��t���L�c�_�Ђɔ��܂��Ă���ƁA�����̐�l�����̒n���w������
��h���s������Ղ������B��h�𐬔s�����h�s���������������_�Ƃ��A���̗�Ţ�\��ʊω������{��
�Ƃ������@���h�ю��Ɩ��t�����B���͈ꎞ�A����76���ɋy�ԑ厛�@�ɔ��W�����B��ɐM���ɂ��Ă������A
�V�ЂȂǂŔp���ƂȂ������ߔN�ɍċ������B�i���@�g�o���������̗v��j
 �@
�@
���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��Q���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�{���i�{���͏\��ʊω��j����������@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ 
���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�����@�E�͉r�̔�@�N���b�N�Ŋg��
��r���u���D�̂܂�ւ�ɘh�ю��䂪�g�̑D�̏o���m��ʂ��v
���͖{���̕��d�@�{���̏\��ʊω��͔镧�łS���Q�P���ɂ̂݊J���A�ʐ^�̊ω��͑O�����̊ω���

���{�s�ɂāi�V���j�@�Z�b�R�h�ю� �O�@��t���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@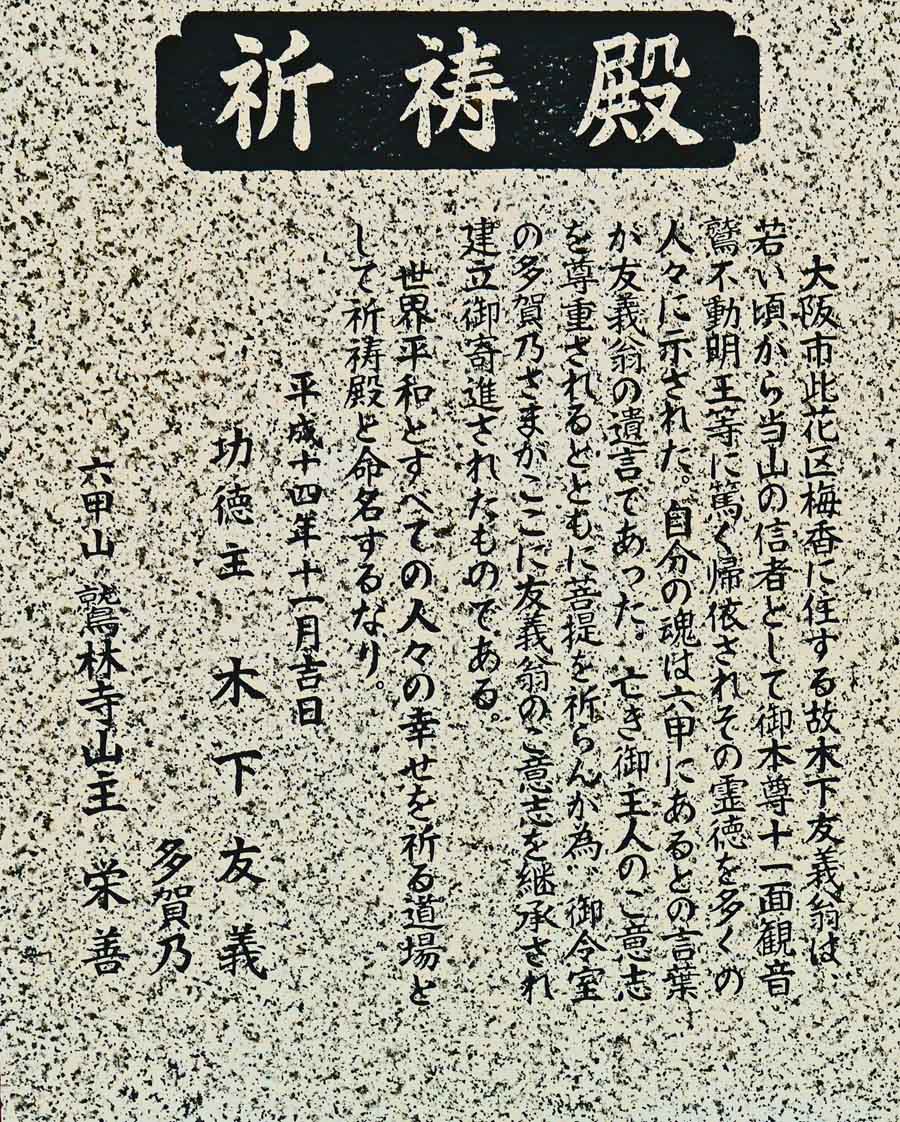
���{�s�ɂāi�V���j�@����R�^���@�Z�b�R�h�ю��@�얀����F���a�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@���������嗳�����A�r�_���A�ٓV���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@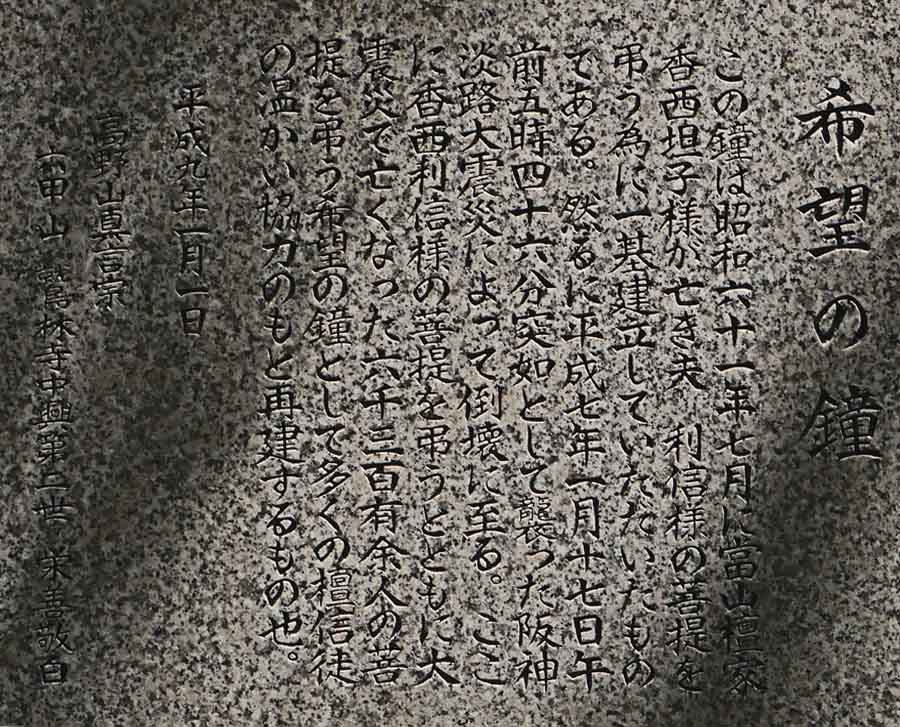
���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@���O�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
���a�ɕ����������O�͍�_�W�H��n�k�œ|�������A��]�̏��Ƃ��čĕ��������B
 �@
�@ �@
�@
���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@����f���h�̎萅�@�����͎������@�E���Z���ב喾�_�Ǝq�����n���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@��������n���@�����n���@���q�n���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���{�s�h�ю��ɂāi�V���j�@�����̐Ε��@�E�͐Α����d���i�`���̕��c�M���̋��{���Ȃǁj�@�@�N���b�N�Ŋg��
���{�s
���{�s
�^���@�䎺�h�ʊi�{�R
�b�R�_��
�i�b�R��t�j
���̃y�[�W�̖ڎ���
�b�R�̏~�a�V�c���菊
�J�n�ȗ��A��1200�N�ɂȂ�Ù�
�����{���Q�q���ꂽ�c���䂩��̎��@
�~�a�V�c��l�ܐ^�����O�i�@�ӓ�j�́A�@�ӗ֊ω��ւ̐M�������A�V��5�N�i828�j�����@���i�Z�p���j�ŏC�Ƃ����A
�l��{�E���{�_���A�A�c�_������b�R�ւƓ����Ă������B���̎��A�܂���C�̋��͂̂��ƁA�_�ɂďC�s���s�����Ƃ����B
�V��7�N�i830�j��C�͍��̖�܂̑傫�����@�ӗ֊ω��������A�{��(�镧)�Ƃ��āA�V��8�N�i831�j�{���͗��c�����B
�_��(����)�Ƃ̓}���g���A�^���Ƃقړ��`�ŁA���̐^�̌��t�Ƃ����Ӗ�������B���̏d���Ȃǎw�蕶�����������B

���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j
����ɍb�R���{�R���Q����茩��@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�P�Q���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@����ɍg�t�̍b�R������@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���@�b�R��t�@�m���� ���͓������A�E�͐��ʂ��@�N���b�N�Ŋg��
�@���̐m����͒����ɍ������l�r����\���A���E�ɒቮ����i�Ⴂ�ɎO�Ԉ�˔��r��ٌ̈^�ł���i���������j
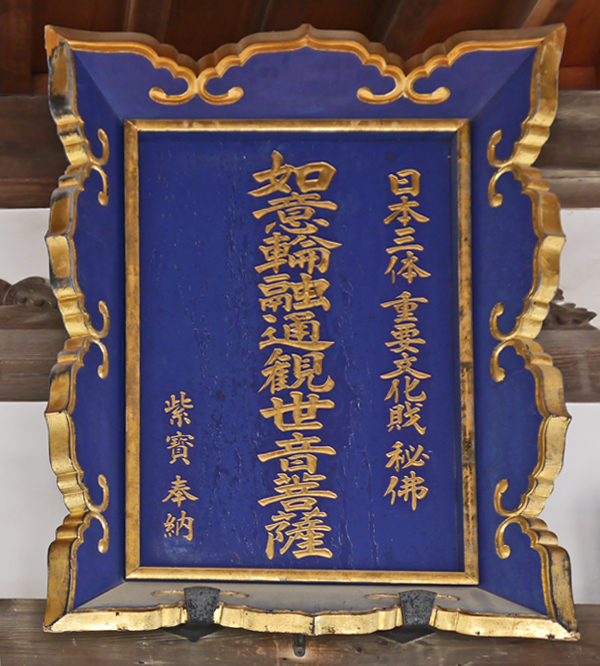 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�@�{���@���͝G�z�@�E�͓���
�{�����ؑ��@�ӗ֊ω������͑��̊ϐS���A�ޗǂ̎������ƂƂ��ɓ��{�O�@�ӗւƏ̂����B�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�P�Q���j�@�^���@ �b�R�_���i�b�R��t�j�@�ӏH�̖{���ƎR��@�N���b�N�Ŋg��
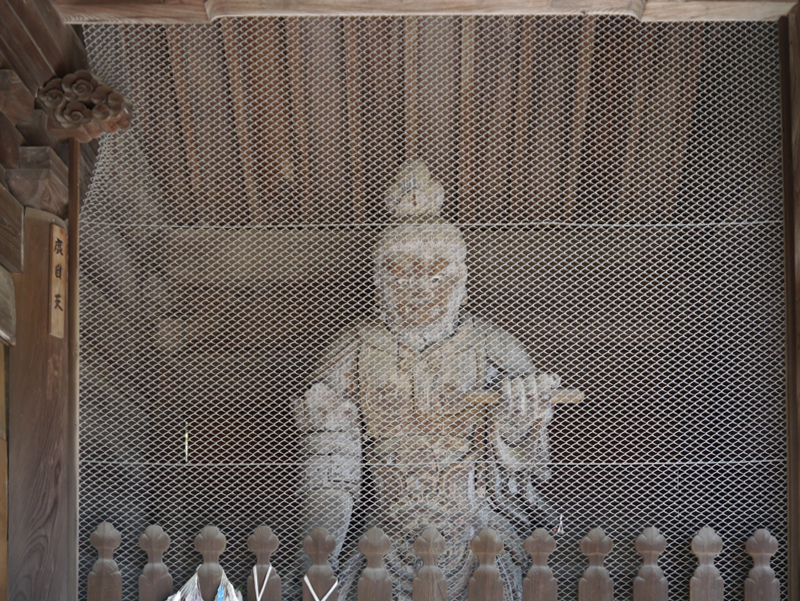 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���@�b�R��t�@�m�����i���{�s�w��d���������j
���m���͍L�ړV�@�E�m���͑����V�@���R�̎w�蕶�����ꗗ�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�Q���ƐΕ��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�@�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@����ω����@�N���b�N�Łi�P�Q���j�g��
 �@
�@  �@
�@ �@
�@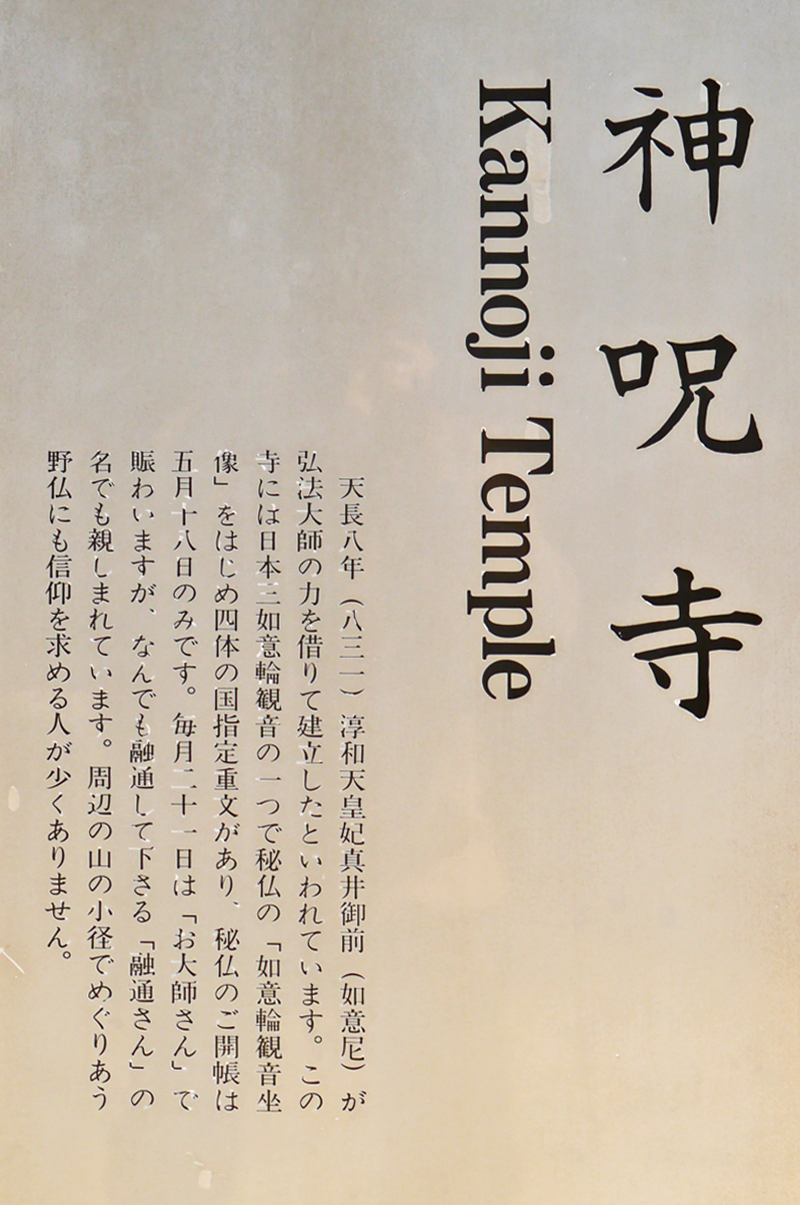
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�{��
���͒������В��^���ΑK���@�E�͕o��ḑ��ҁ@�E�[�͓��R�̊T�������@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@���O�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�������Ƒ�t���@�N���b�N�Ŋg��
���[�ʐ^���_�ɂāi�P�Q���j�@�g�t�̍��̏��O�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�ɂāi�S���j�^���@�䎺�h �b�R�_���i�b�R��t�j�@�ω����ƕs�����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�^���@�䎺�h�b�R�_���ɂāi�S���j �@�ٓV���ƍb�R�i�N���b�N�ōb�R�̈���蕶�j�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�^���@�䎺�h�b�R�_���ɂāi�S���j �@�����̍��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���ɂāi�S���j ���ɐ�w�@�ԗ쓃�ƍ����{�L�O�A����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@������萅�ɁA�o�l�ˁ@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j �@������R������@�ӏ�ˁA�Ԓˁ@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j �@�����狛���ˁA�ӏ�ˁA�Ԓ��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t2�j�ɂāi�S���j�@���������Ò|�R�u�L�O���A���w�R�l�̔�A��ˁ@�N���b�N�Ŋg��
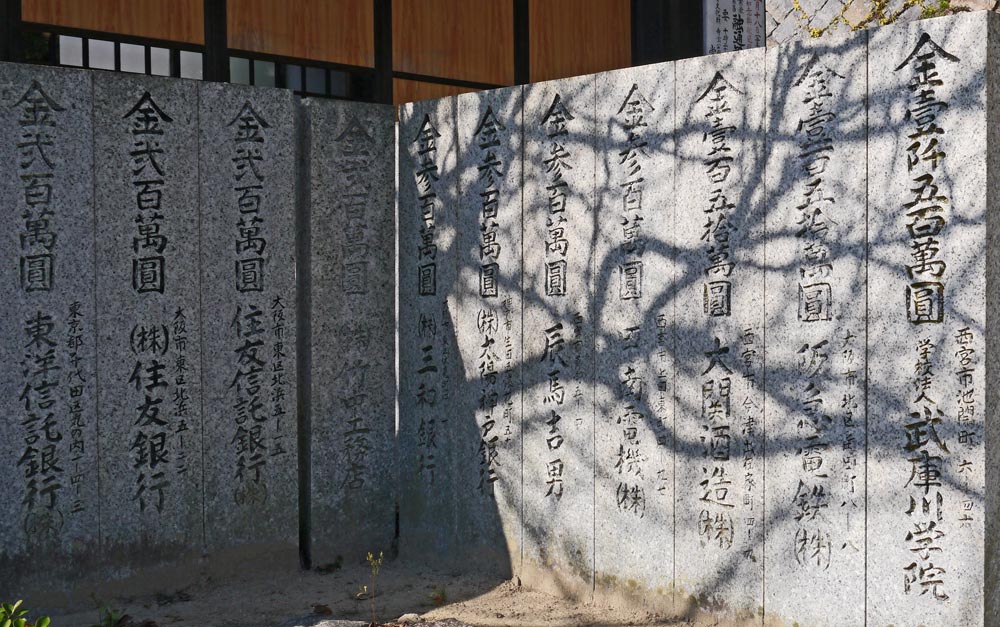 �@
�@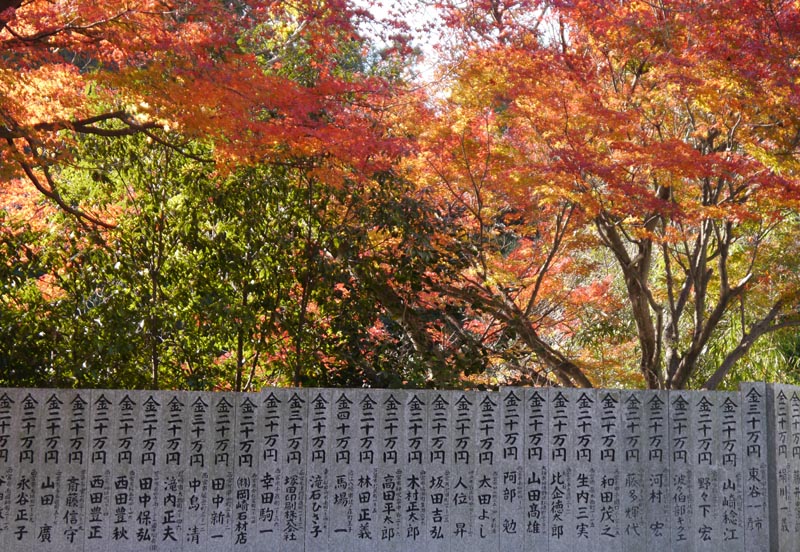
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t2�j�ɂāi�P�Q���j�@��i�҂Ƌ��z�����ʊ_�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j�@���s�����ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��
�@

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�P�Q���j�@���s�����ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@���s�����ʂƐ��{�s�k���i���w�@�j���ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��

���Ɍ����{�s�b�R�_���i�b�R��t�j�ɂāi�S���j�@���p���ʓW�]�@�N���b�N�Ŋg��
���R��
�_�ˎs����
�V��@
�O�g�R���R��
���̃y�[�W�̖ڎ���
���������̒��j��b�i���傤���j���J�R�A���̓����F������������������
�����V�c�̒��莛�Ƃ��ė�T2�N�i716�j�ɔ���ҁE���������̑��̓����F�����������������������B
�J�R�i����Z�E�j�͓��������̒��j�E��b�i���傤���j�Ƃ����B�n�����̌����͍O��8�N�i1285�j�ɏĎ����A
���������͂���ȍ~�̍Č��ɂ��B�J�R���b�i��͓����s�䓙�j�͎Ⴍ���ďo�Ƃ��A�����g�ƂƂ��ɓ��ɓn�����B

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���{���i����j

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���m����i�d���j
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�Q�� |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�V����25�Ԕ� |
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�Q��
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����

�_�ˎs����ɂāi11���j�@�V��@�O�g�R���R���{���i����j
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ� |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j �{���̂т鑸�� |
 �@
�@ 
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ�
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@����ɓ��ƈ���ɔ@�������i�d���j�i�N���b�N�g���j
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�O�d�� |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�O�d��  �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�萅�ɂƎO�d�� |
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�얀���@�@�E�͌얀�d
�@�@
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�n���� |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�����r |
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�m����i�d���j�̓����i�N���b�N�Ŋg���j�@�@�E�͏��O
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�������@�@�E�ʐ^�������̌���Ɏ߉ޓ��̉����̐�[��������
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@���R����脉��䋴 |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j ���̉@�̈��  �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@脉��䋴 |
 �@
�@
�_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@���q��
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j�@�L |
 �_�ˎs�������R���ɂāi11���j ���Ɉ�ב喾�_ |
���R���������{�@
���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@���w�薼�� �͒r���͎R���뉀

�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@�͒r���͎R���뉀
���w�薼���뉀
 �@
�@
�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�R��@�@�R������ƌ���
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�@���@ |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�뉀�����t�� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������{�@�S�i |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�Q�� |
 �@
�@ 
�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�뉀�@�@
 �@
�@
�_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���{�@�@�L����1�@����萅���i����Ύ萅���j�@�E�ʐ^���L���̂Q
���R���������ۉ@
���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs�������R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�O�� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j �������ۉ@�@�u�Ǝq����v�̔� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@�������ۉ@�R�� |
���R���������A�@�����@
���̃y�[�W�̖ڎ���
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@���A�@�O�� �ʐ^�N���b�N�Ő��A�@�뉀�̐����� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j �������A�@�R�� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j�@����@�O�� �ʐ^�N���b�N������@�뉀�̐����� |
 �_�ˎs���摾�R���ɂāi�P�P���j ��������@�R�� |
����R
�_�ˎs�k��
����R�^���@
���R����
���̃y�[�W�̖ڎ���
��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù�
�V���I�ɍF���V�c���J�����Ù��Ŏ��\�]�̎q�@�i���݂͒|�ю��Ə\�։@�̂݁j
�����厛�@�ł������B�{�R�ƊW���铿�쏫�R�A���d���̒W�͏��L�n�����̕揊������
���2�N�i651�j�F���V�c�̒���ɂ���C���h�̑m�@�����J�R���A�����n����F��{���Ƃ���B�V��19�N�i747�j�A
�s���t�����������A�O�m14�N�i823�j����V�c�̒���ɂ��O�d�������������Ɠ`���B
�d�����E�ł������ԏ����A�R�����Ɋւ�邱�Õ����������B

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q�����{��

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���@�@�Ε������N
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@��t���i�d���j�@�E�͂т鑸�ҁi�N���b�N�Ŋg��j
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���E�̖�t���@�@�ʐ^�E�͖{��������̑�t�䒃��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�{���̝G�z�@�E�ʐ^�͖{������^��������
 �@
�@ 
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�n�������@�@�E�͍F���V�c���菊��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�����̎U�݂���n������
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���O�@�E�͒��v�ݐ��ω����i�N���b�N�Ŋg���j
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�m����
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�m����̐m���i���E��j

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�Q��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�������R

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R���
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R����@�W��㓿�쏫�R�A���Ώ��A�W�͏��̕�
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���쏫�R���
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�O�d���i�d���j�@����@�����J���Ă��� �@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@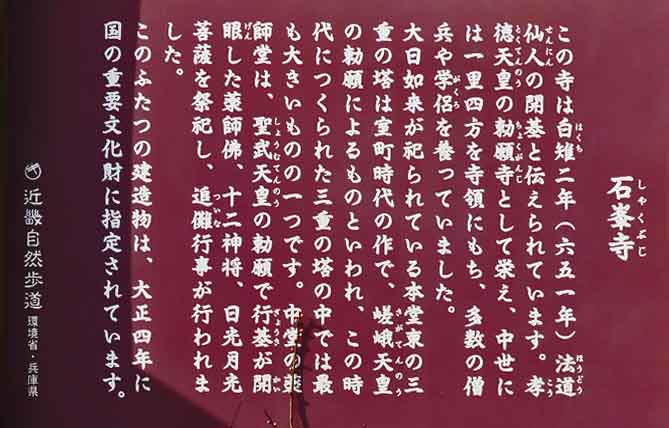
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�O�d���i�d���j�@�E��D�̓N���b�N�g��
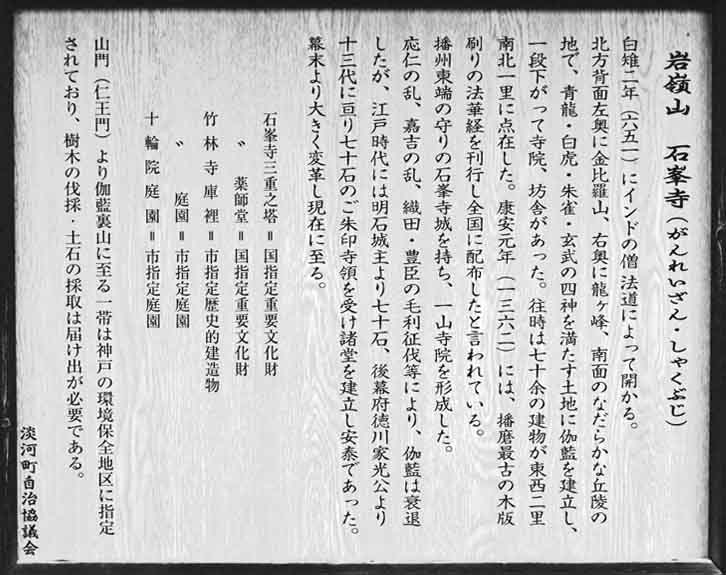 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�萅�@���̋�D�̓N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@���\���ӏ����߂���

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�t�߂̔d���̕��i�i�Z�b�R���]�j

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�t�߂̔d���̕��i�i�Z�b�R���]�j
�Ε����q�@�@�|�ю�
�_�ˎs�w��뉀

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��R��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��뉀�i�_�ˎs�w��j�@�����͎��\�]�̎q�@��������

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��뉀�i�_�ˎs�w��j
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю���������O�����@�@�E�͎R��O

�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�|�ю��̊������{������
�Ε����q�@�@�\�։@
�_�ˎs�w��뉀
 �@
�@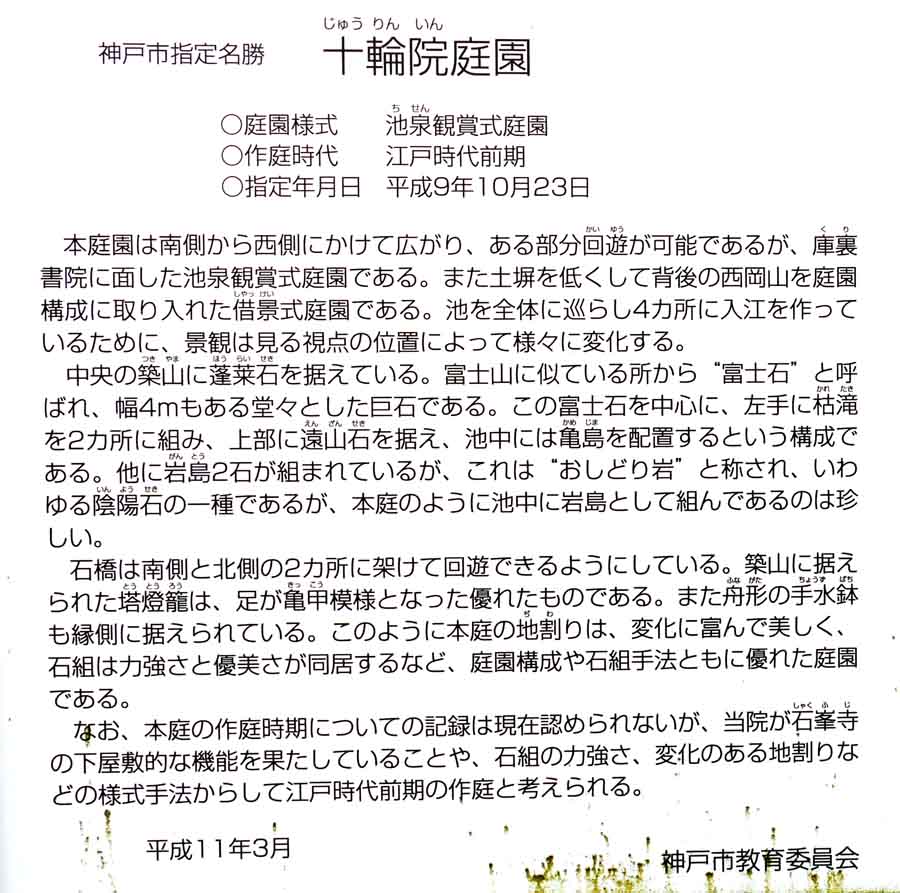
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@�@�E�͏\�։@�뉀��D�i�N���b�N�g���j
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����@�q�@�@�\�։@�i�_�ˎs�w��뉀�j
�W�͒�
�_�ˎs�k�� �W�͒�
�����@
����R�ב���
���̃y�[�W�̖ڎ���
�_�ˎs�k��ɂāi�Q���j�@����R�^���@���R�Ε����̋A�H�ɍ݂�����

���Ɍ��W�͒��ɂāi�Q���j�@�����@�@����R�@�ב����i�i�����������j�j

���Ɍ��W�͒��ɂāi�Q���j�@�����@�@����R�@�ב���
�C���@
�O�؎s
�{�R�C���@
��J�R��R�������@
���̃y�[�W�̖ڎ���
��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù��B�F���V�c��ԎR�@�c
�䂩��̎��B�G�g�̎O�؏�U�߂œ����Ƌr���Ď��̐m�����o�}����
�F���V�c�̒��莛�œV���̖@����l���J����Ɖ]���B��殎��i�����������j�Ə̂��A1681�N�Ɍ㐼��c�ɂ���
�C���h�̐��n���ɉ���Ɉ��݁A����@�Ƃ����B�d���n���ɑ����@���J��`���������@�̈�B��������ɂ͐��\��
���F�ƕS�O�\�]�̖V�ɂ������A�ԎR�@�c���s�K�����B�H�ďG�g�̎O�؏�U�߂ŁA�ʏ������̐w�ƂȂ������R��
�Ί_���c���đS�R���Ď������B�������铰����1610�N�ȍ~�̏����喼�̊�i�ɂ����̂ł���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�m�����@
�G�g�ɂ��ꕔ�Ď������m���̋��Ɠ������u�@�ʐ^�N���b�N�ʼn���@�̐��������o�܂�
 �@
�@ �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�m����̏Ă����m�����̈ꕔ�@�����̎ʐ^�N���b�N�Őm����̐��������ł܂�

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E���������@�N���b�N�ŋ�D

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{�V���̖�\���@�N���b�N�ŋ�D
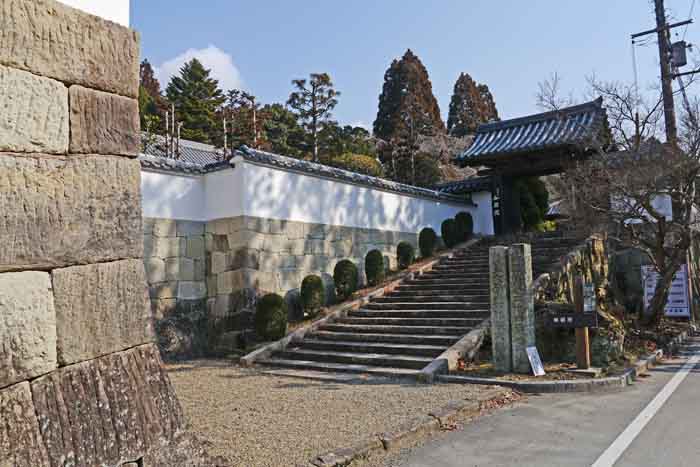
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R�@��殎� ����@�@�{�V���̖�\��
 �@
�@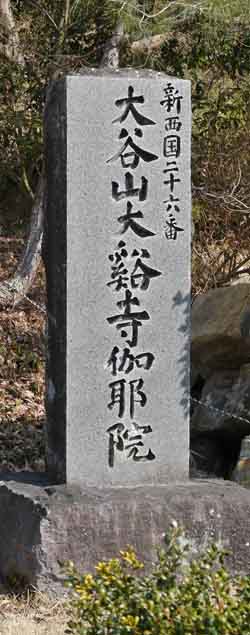 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@��V���@�]�ˏ����̔��r���i�N���b�N�������j�@����Ɠ�V���G�z�i�N���b�N�g���j
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@��V���̓�V�i�N���b�N�Ő�����D�j
 �@�@
�@�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{���i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D���g��\��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�{���i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D���g��\��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�얀����@�N���b�N�Ő�����D�@�E�ʐ^�͋����̈ē���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�s�ғ��i�s�w�蕶�����j���s�҂̂����蓰
�y�����̊�i�ɂ��@�ʐ^�N���b�N�Ő��������ł܂�
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�s�ғ��i�s�w�蕶�����j���s�҂̂����蓰�@�y�����̊�i�ɂ��@�ʐ^�N���b�N�Ő�����
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@������V�̉������@�ʐ^�N���b�N�Ő��������o�܂�
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�J�R���@���ɉE�߂̊�i�œV������̖@����l���J��@�N���b�N�ŋ�D

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�J�R���@�N���b�N�ŋ�D
 �@
�@ �@
�@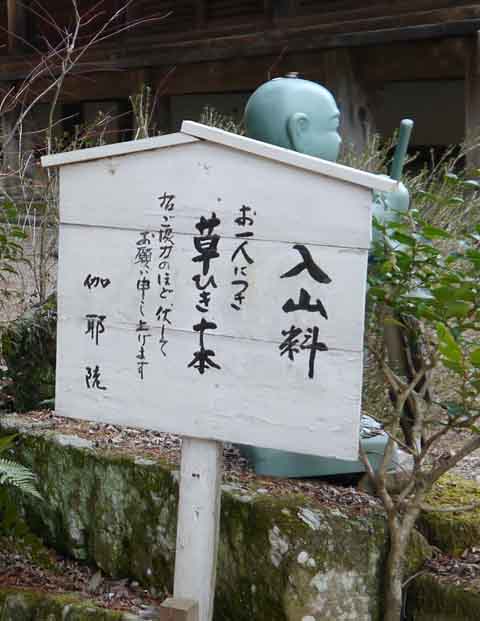
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�o�ˁ@�ʐ^�E�͓��R���������\�{�̗��D
 �@
�@ 
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��喾�_�i�d���j�@�N���b�N�Ő�����D�@�G�z�̓N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��Ёi�E���ʁj�N���b�N�Ő�����D�@���Ԃ̓N���b�N�f�g��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�O��Ђ̏ۂ�富҂̒����@�ʐ^�N���b�N�f�g��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���i�d���j
�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E�ɗ��t��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�[�o���E�ɗ��t��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@ �[�o���E�ɗ��t��
 �@
�@
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���ʐ^�͔[�o���@�@�E�͖{�V�ɗ��Ǝv���闧�h�Ȍ���

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�萅

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�P���
�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��
 �@
�@ 
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�����̐�n��

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@
���ǂ��|�b�N������i�N���b�N�Ő����j

�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@���q�n��
 �@
�@ 
�O�؎s�ɂāi2���j�@��J�R ��殎� ����@�@�L�������@�@�@�E�͎Q���i�O���͐m����A����͓�V��ւƑ����j
�^���@
����s
����R�^���@
�Ɋy�R��y��
���̃y�[�W�̖ڎ���
��y���͓��厛�ċ��̂��߂ɐ݂���ꂽ���厛�d���ʏ�
���厛�ċ��҂̏d�����{���̊J�R�ŁA����̑刢��ɎO������������
����4�N�i1180�j�A���d�t�̏Ă������ŁA���厛�̑啧�a�A���������Ă��������B���̑啧�̍ċ��̑��ӔC��
�ƂȂ����d���͑啧�ċ����Ƃ̋��_�Ƃ��āA�ɉ�A���h�ȂǓ��{��7�����ɓ��厛�u�ʏ��v�����B���̈��
�d���ʏ��E��y���ł���B��y���̏��ݒn�͓����A���厛�̂ł������B��y���̊J�R�A
�����y���̈���ɎO�����ݎ҂͓��厛���ċ������d����l�ł���B

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�Q���@���ʂ͏�y���i����j
�ʐ^�N���b�N�ŋ����} �@�@�p���t���b�g�̋����}

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�@�N���b�N�œ�������ɎO����
 �@
�@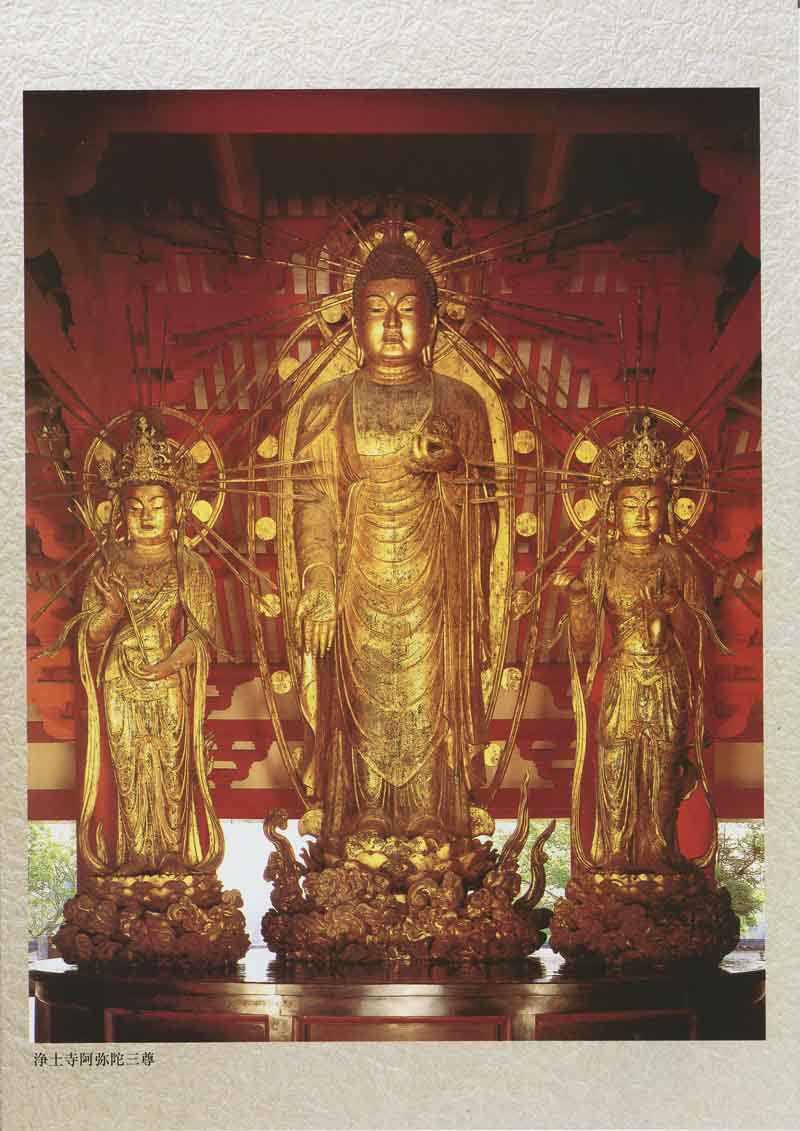
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�@�ʐ^�E�͓����̈���ɎO���i����j
�ʐ^�E�͒����Ɉ���ɔ@���A���Ɋω���F�A�E�ɐ�����F�i���@�p���t���b�g���j�@�N���b�N�Ŋg��
�����̈���ɑ���5m30cm�A���e�̕�F��3m70cm�Ƒ傫���B�d����l�̌����A���t���c�̍�B
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��y���i����j�ʐ^���͎w�蕶�����ꗗ�\�i�p���t���b�g���j
�p���t���b�g���N���b�N����Ɗg�債�܂�
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@���O���i���d���j
 �@
�@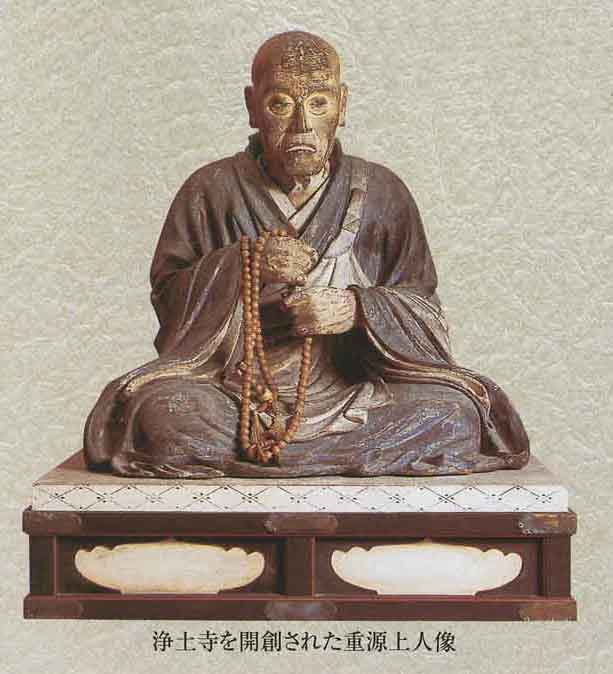
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�J�R���i���d���j�ʐ^�N���b�N�ŋ�D
�ʐ^�E���p���t���b�g�̊J�R�d����l�̑��i�N���b�N�Ŋg�債�܂��j
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@����

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�o���ƕ��ꓰ

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y��
�����@�N���b�N�����g��
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�{���i��t���j�i�d���j�@�ʐ^�E�͐��ʁ@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�s����
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����@
�ʐ^�N���b�N�œ����i��y���ł͓����Ƃ������j������

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��������@
�ʐ^�N���b�N�œ����i��y���ł͓����ƌ���Ȃ��j������
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@��������@

���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_��
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_�Ж{�a�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�Ő�����D
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�����_�Дq�a�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D
 �@
�@
���Ɍ�����s�ɂāi�U���j�@����R�^���@�Ɋy�R��y���@�Q��
 �@
�@
���Ɍ�����s����R�^���@�Ɋy�R��y���ɂāi�U���j�@�A�W�T�C�@�A�W�T�C�ȁ@�A�W�T�C��
�V��@
�����s
�V��@
�@�؎R��掛
���̃y�[�W�̖ڎ���
�������\�Z�ԗ��
��1400�N�O�V���̖@����l���J�����Ù�
�O�g�t���̔��|�����@����l���J����
��掛�J��A�@����l�͖�1400�N�O�A�V�����璆���A�S�ς��o��
���{�̔d�B��ΌS�i�����s�j�ɍ~�藧���A������@�،o�̗�R��@�؎R�ƍ���
���ƌ����B�@���͐_�ʗ͂���A��l�ƌĂ�A�]���͓s�ւ��L�܂�A
��賌��N�i650�N�j�F���V�c�̒����Ŗ@������掛�����Ă��Ƃ����B
�]�ˎ���ɂ͕P�H��̏��{�c�Ƃ��x�����B

���Ɍ������s�ɂāi�X���j�@�������\�Z������@�V��@�@�؎R��掛
�����i��ߊt�j�i�d���j�@�ʐ^�N���b�N�Ŗ@�؎R�ē��ց@��r�̂�
�u�t�͉� �Ă͋k �H�͋e �������Ȃ�@�̉؎R�v
�Ɖr��ꋫ���ɂ͋k�������A�т���Ă���
 �@
�@
���Ɍ������s�ɂāi�X���j�@�V��@�@�؎R��掛�@���ʓ����@������
�g�t�̍��̎ʐ^���@��掛����T�C�gYOUTUBE��
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�@�Q�� ��s���O�����Ԗڂ̐Βi |
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�@�Q�� ���ʓ��������Ԗڂ̐Βi |

�����s�ɂāi�X���j�@�V��@�@�؎R��掛�@��s��
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j |
 �V��@�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �����G�z�u��ߊt�v �@�����z�u�}�l�b�g1 |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����i��ߊt�j�w�� |
 �@
�@
�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���O

�����s�ɂāi�X���j�@�������\�Z�ԁ@�V��@�@�؎R��掛�@�O�d���Ƌ����i��ߊt�j
 �����s��掛�ɂāi�X���j�@�O�d���i����j �@�@�@�@�@ |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �O�d���i����j�ʐ^�N���b�N�Ő����� |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j �O�d���i����j |
 ���@�̍Ő����i����j �l�b�g���]���@�N���b�N�g�� |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�ٓV���Ɩ������i�d���j |
 �����s��掛�ɂāi�X���j�@��@���i�d���j �����s��掛�ɂāi�X���j�@��@���i�d���j |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���̉@�ւ̎Q�� |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@���q�喾�_�@������ב喾�_ |
 �����s��掛�ɂāi�X���j�@���q���@�����}�l�b�g2 |
 �����s��掛�ɂāi�X���j�@�s�ғ� |
 �@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�����r |
 �@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�O�d���Ə�s�� |
 �����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�{�V�@�n���@ |
 �����s��掛�ɂāi�X���j�@�{�V�A�n���@�� |

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@�V�ّS�i

�����s�@�؎R��掛�ɂāi�X���j�@��
�@�؎R�א��@
�i��傤����j
�@�؎R��掛�̌��������@
 �@�@
�@�@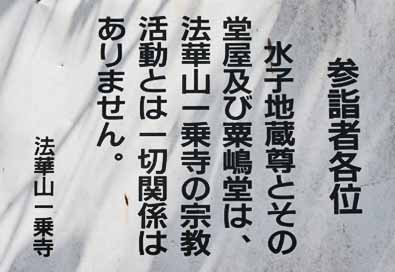
�����s�ɂāi�X���j�@�א��@�n�����ƈ�掛�̊Ŕ�

�����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@�R��i���u����̎���j
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@���q�n���� |
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�O���א��@�@������ |
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�O�̗א��@�@�R�� |
 �����s�ɂāi�X���j�@��掛�O�̗א��@�@���q�n���� |
���|��
�O�g�s�t��
�V��@
���|��
���̃y�[�W�̖ڎ���
�V���̖@����l���J�����Ù�
��ړ��ŗL���A�t���ǂ̏o�g�n�ł�����
���|���͂��c�_�Q�N�i705�N�j�@����l�ɂ���ĊJ�c���ꂽ�Ù��ŁA�{����
�V������`����ꂽ�ƌ�����t�ڗ����@��(�镧)�B���Ԃ̔��|����_�X����������
�����Ă������߁u���|���v�ƌĂꂽ�B ����Ɍ��Ɠ�k������̗̎�ԏ�����
��⸈��`���ق��A�t���ǂ̕��A�ē����O���M�̉��m�c����Ă���B
���ӂ̓��́u��ړ��v�ƌĂ�A���N�A��ڂӂ��܂肪����ɍÂ����B

���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�ʐ^�N���b�N�Ő�����
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�Q�� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@���O |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�R�� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�{�� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ���{�����t���@�@�N���b�N�Ŗ�t���\���� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ���{�����t���@�쑺���݂� |
 �O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@���ۋ� |
 �O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�S���r |
���ۋ��̋}���z�́A���ւ̓��̂�̌�������\�����Ă���B
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �n����F�� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j ������Ƃ炷�蕶 |

���Ɍ��O�g�s�s���@���|���ɂāi�T���j�@��ړ��@�}���ȁ@�t�W��
�@
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@�M�\�� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j�@��r�̐Δ� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �ԏ���͂���⸈��i���d���j�@�N���b�N�Ő����� |
 ���Ɍ��O�g�s�V��@�ܑ�R���|���ɂāi�T���j �F�쌠���Ё@�N���b�N�Ő����� |
���ю�
��ˎs
�^���@
���ɎR���ю�
���̃y�[�W�̖ڎ���
�p���V�c�̖��Ő������q���n���̌Ù�
��O�͐��{�X�� ��������}���Ð�������
���ю��͕�ˎs�ɂ����^���@�P���̎��@�B���Ɏ�����1�B�{���͎߉ޔ@���B
�����͓����^���@���A�@�A����R�^���@�����@�A�^���@��o���h�����@�A���h����@�B
���`�ɂ��A����A�p���V�c�̖��Ő������q���n�����A
��������ɔ@��ċ������Ƃ����B�i�Q�l�j

��ˎs���тɂāi1���j�@�^���@���ɎR���ю��i�ւ���j�@
 ��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@��t���@ |
 �@��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�{���@ |
 ��ˎs���тɂāi1���j�@���ю����������^���@���A�@�@ |
 ��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�ω����@ |
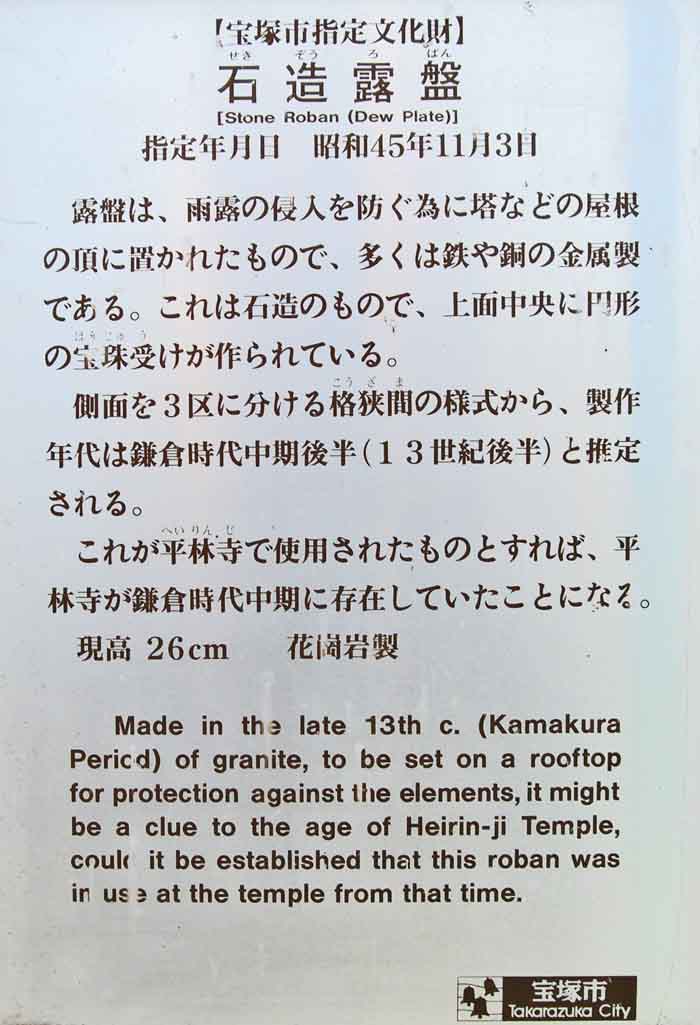 ��ˎs���тɂāi1���j�@ ���ю��Α��I�Ր����@ �N���b�N�Ŋg���@ |
 ��ˎs���тɂāi1���j�@���ю��@�Α��I�� |
�~����
���{�s
���{���c�R�E�㉤�R�~����
�@���̃y�[�W�̖ڎ���
 �@���{�s�ɂāi�P���j�@���{���c�R�@ ��t�����c�R�V�������s���������� |
 �@���{�s�ɂāi�P���j�@�㉤�R�~���� �{���@ |
�i�V��
�O�c�s
�����@
���R�i�V��
���̃y�[�W�̖ڎ���
���Ԃ̎�25���̈��
���傤�ԉ��A���O���A�Ԃ̂��イ����Œm���閼��
�@�i�V���͉����N�ԁi1370�j���A�������{�Ǘ̐E�א엊�V����~�Z�V�c�̖��ɂ�莵���������������A�ʌ����T�t���J�c
�Ƃ���T���B�����@��{�R�`�����i���l�s�ߌ��j�̒����ŁA������17�J���B�ʌ��T�t�䂩��̒ʌ��h���@��8,900�����𐔂��A
�䍑�ł͍ő勉�̏@�c�ł���B�{���͎߉ޔ@���A����@���A����ɔ@���B�H�t�a�ɂ͉Ζh�ɗ쌱���炽���ȏH�t�O�ږV�匠���A
�J�c���O�ɑ�n����F�A�����t�ɑ�ϐ�����F�A����̐M�M�R�{��������V�̌䕪�g���J���Ă���B�����́A���i7�N�i1778�j
�ɍČ����ꂽ�{���A�J�c���A�ɗ��A�ڕo�A���@�ƁA���a40�N�̑䕗�ŕ��A�Č����ꂽ���g��i�������j�̂ق��A�ʓe��A
���{��A�R��i�m����j�A�����t������B�����n16000�A40�����̎��L�т�6�����̎O�c�쉀�A�����쉀�����L�����B
�i�ȏ�͉i��HP���j�@���Ԃ̎�25��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�@���Ԃ̎�25���̈��
 �@
�@
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�̐m��

���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i���i�悤�������j �{���ւ̎Q��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���@�{���@�{���͎߉ގO��
 �@
�@
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���ʓe��@�@�ʐ^�E�͊������̒��g��
 �@
�@ 
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i�����g��i���a40�N�̑䕗�ŕ��Č����ꂽ�j
 �@
�@
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���@�����t���L���@�@�ʐ^�E�͋��{��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�O�̒r
 �@
�@
�O�c�s�ɂāi6���j�@�i���R��i�m����j�O�̒r
 �@
�@ 
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���̖�i��O����ʓe��A���g��A���{��j�@�@�ʐ^�E�͎R���������E�̎萅��

�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�����̊ω����@�O���ɒ��g��
 �@
�@
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���R��i�m����j�ڂ̎Q���@�@�E�ʐ^�͖{��
 �@
�@
�O�c�s�i�ɂāi5���j���Ԃ̎�25�����i�̉��@���J�̃~���}�I�_�}�L�ƃX�Y�������̑����킠��
 �@
�@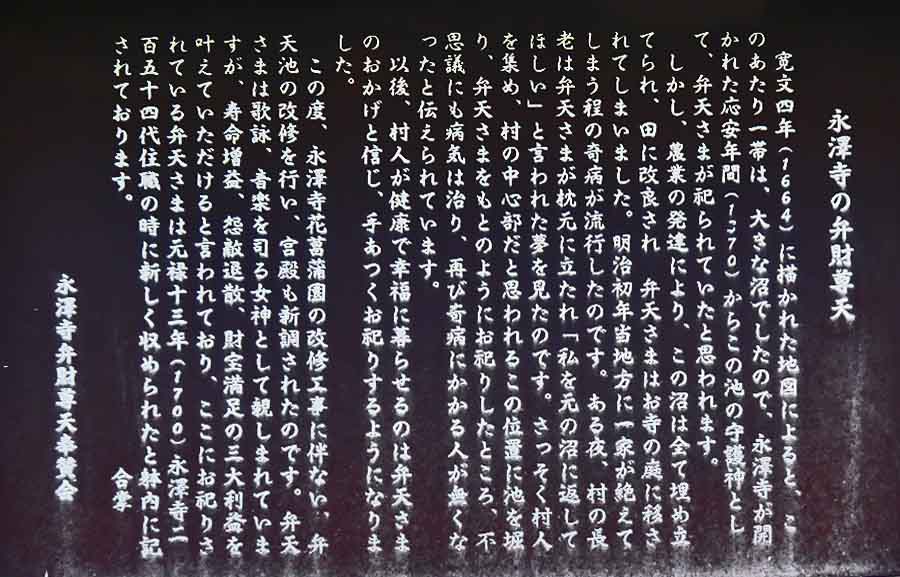
�O�c�s�ɂāi5���j�@�i���ٍ̕����V�i���傤�ԉ��̒��ɂ���j�@�ʐ^�N���b�N�ŋ�D�g��\��

�O�c�s�i�ɂāi5���j�@�i��O���Ԃ̂��イ����
 �@
�@
�O�c�s�i�ɂāi6���j�@���O���E�ԏҊ����@�O�c�s�̊ό��X�|�b�g�@�ԏҊ����@�A�����ȁ@�A������

�@���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i�����Ҋ������W�]�@
 �@
�@
���Ɍ��@�O�c�s�ɂāi6���j�@�i�@�L���@�@�@�@�@�@�@�@�Ҋ������i�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�O�c�s�i�ɂāi5���j�@���O���E�ԏҊ����̉��O
 �@
�@
�O�c�s�i�ɂāi5���j�@���O���E�ԏҊ����̉��O
�ԎR�@
�O�c�s
�^���@
�����R�ԎR�@���
���̃y�[�W�̖ڎ���
�ԎR�@�̕�@�����O�\�O�ω����ԊO�n
�J�R�͈�掛�Ɠ����V���̖@����l
��賂Q�N�i615�N�j�V�����n�������@����l���B���{������t�ڗ����@���B
��ɐ����O�\�O�ω���ꒆ���̑c�A��Z�\�ܑ�ԎR�@�c(�ԎR�V�c)�����O�T�N(1008)
��N41�˂Ō���䂳��閘�A�����ŕ����C�s�ɗ�܂ꂽ�B�@�c�̂���̂����̎���
�����A���ꂪ�ԎR�@��_���ł���B�ȗ����R�͉ԎR�@�c�i�ԎR�@�j�̕���
�������Ƃ��ĉԎR�@��������Ƃ���Ɏ������B

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����
 �O�c�s�����R�ԎR�@�ɂāi7���j�@�萅�̒n�� |
 �@ �@ �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����̐m���i���E�j�@ �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�m����̐m���i���E�j�@ |
 �@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@ �m���傩��{���ւ̎Q���@ |
 �����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�{���@�ԎR�@�c�a �\��ʊω����@�ԎR�@�c���@�O�@��t�������u����Ă� |

�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�{���ԎR�@�c�a�i���j�Ɩ�t���i�E�j
 �@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@��t���@ �@�{���̌������ĉE�ɍ݂�A��t�@�������u����Ă���@ |
 �@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@ �ԎR�@�c��ˏ��@ |

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�K���̎��n���@�@�ʐ^�N���b�N�Ő����@
 �@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���O�@ |
 �@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@��������i�E�ɍr�_�Ёj |
 �@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���������̂�������1�@ |
 �@�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@���������̂�������2�@ |

�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@����������̓W�]�i���ɗL�n�x�m,�A�E�ɐ�䎛�j
�ԎR�@���䐻�ɂȂ�{���̌�r�́B
�u�L�n�x�m�@�[�̖��͊C�Ɏ��ā@�g���ƕ����Ώ���̏����v
 �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�O���r�_�@ |
 �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j�@�O�@��t�� |
 �@
�@
�@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi7���j �@�ԎR�@�W�]�䂩��L�n�x�m�Ɛ�䎛��
 �@�O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi8���j�@�ɗ��@ |
 �O�c�s�@�����R�ԎR�@��ɂāi8���j�@��t���@�ڗ����a |
�����@
�_�ˎs�k��
�����@
�܌؎R������
���̃y�[�W�̖ڎ���
�s��ɂ��J�R�Ɠ`���Ù�
���R�͐������q�̑��n�A�s���F�J�R�Ɠ`������Ù��B�ߐ��C���m�ŒʑT�t�ɂ�蒆���J�R���ꂽ�B
���{���͖�t�@���ŁA�^���@�ł��������A�������N(1804)�����@��{�R�i�����\�����������V�t����������A
�ȗ��A�i�����������ƂȂ����B���a40�N�����玛�����Z�ƂȂ�r�p���i���A�Ăь������̕���������Ă���B
�{���̎R���́u�܌؎R�v�ŋߗׂ̓L�ˎ��́u�ƌ؎R�v�A�������́u�O�؎R�v�ł���A�Â�����[���W��
����Ǝv����B����̒n������A���̕t�߈�т��R�x�M�̓���ł������炵���B�i�������j
 �@
�@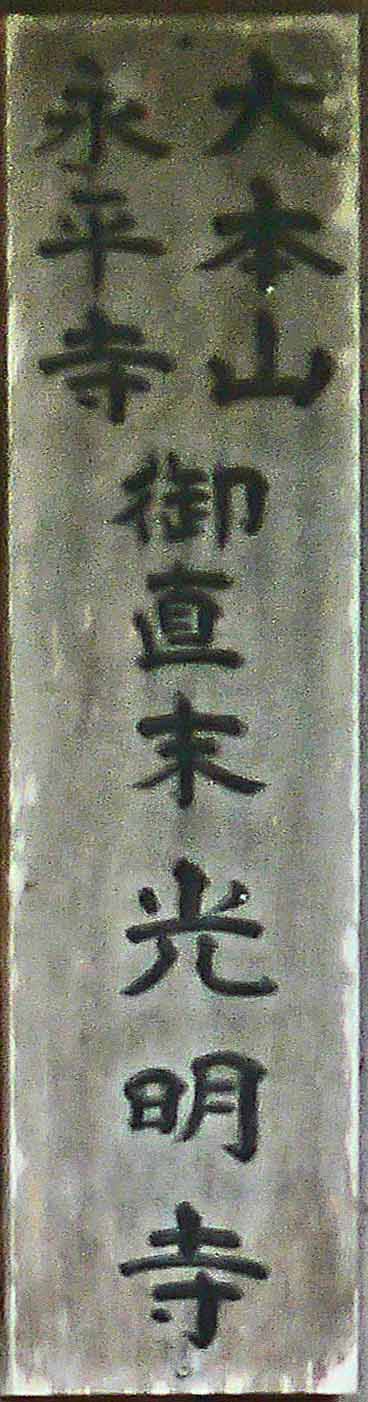
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�ÐF���ӂ��R��@�@�N���b�N�Ŗ�̓���������
 �@
�@ �@
�@ 
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�������猩��R��Ƒ����@�̖�̂��銢�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������J��@�@�ӗ֊ω����J��@�E�͊J��ɂ�����G�z�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ 
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������J��@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@��������n�����@�N���b�N�Ŋg��
�@
 �@
�@ �@
�@ 
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�����̐Ε��E����@���A�n�����@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@�����̐Ε��E�\��ʊω��@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k��ɂāi�W���j�@�܌؎R�������@������ƌ����s�����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@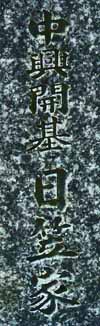
�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@�@���͕Ɋ�@�O���狏�m�@➈@�E�͒����J����}�Ƃ̖@➈�
���́u�Ɋ�@�ꗹ�狏�m�v�͎ēc���̖@���B�@�ēc���͕��ɌS�呺�̐V�݉ƂŁA���m���ʑT�t���L�n��
����ꂽ���A�T�t�ɋA�˂��āA���̐������q���n�A�s��J�R�̗�ՂɁA��F����������i�����B
 �@
�@
�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@���萬�A�̊~�̐_�i�N���b�N�ŗR�������j
�E�͕��Ɍ��ό�100�I�g�t�̖������v�킹�镖������
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k���܌؎R�������ɂāi�W���j�@�犠�����n�i�����j�t�߁@�E�͐犠�_���@�@�N���b�N�Ŋg��
�������ɗאڂ��镐�Ƀm��S���t�R�[�X�̌��������犠�_��
�^���@
�_�ˎs�k��
�^���@�P��
�ƌ؎R�L�ˎ�
���̃y�[�W�̖ڎ���
�������q����̒n�ɁA���q����1400�N�O���J�R����
�Ù��B�h�͐����̌�ɁA���a�ɂȂ��Ė{�i�I�ɕ�������
�������q�́A����̗��ɖ�1400�N�O���q�B�V�c10�N�i�T�W�P�j�A���������ĕ�������Ƃ��ēL����[�A
�L�ˎ��Ɩ������ꂽ�B���̌�A�O�@��t�������ɓƌؐ��̈�˂��@����Ȃljh�������A��A�R�Ύ��Ȃǂ�
���ނƒ������J��Ԃ����B�����U�N�A�O�c��S�˂̓V�n�g���_�Е��t���P���A�������������A�p���ƂȂ����B
��100�N��̏��a30�N�ɋv王{���Z���a�����A�p����K��ɂȂ�A�L�ˎ��̍Č��ƍ��ƍ����̈��J���F��ꂽ�B
�����āA���a34�N�A���R�咆�������t�����R���A��41�N�Ɍ얀��(�s������)���A48�N�ɂ͎O�d��(����F)�A
�����S�N�ɑ���@��������������}���Ė{���̗��c�@�v�����C����A���U�N�ɕٓV���̗��c�������B�i���N���j
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�{���@�@�N���b�N�Ŋg��
�{���͑���@���@�ʐ^���͎Q�������@�@�E�ʐ^�͖{���Ɋ|����G�z
��r�́u�S���i��������j�� �����č��� ���Ԃ����@��������� �͂Ȃ����v
 �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�{���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�E���A�������猩���{���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�얀���Ɩ{���̕s�������@�@�N���b�N�Ŋg��@

�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�L�ˎ��@�q�a��y���z���ɎO�c�s��W�] �N���b�N�Ŋg��
 �@
�@  �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@���O�ƕٓV���ƎQ���@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�q�a�i�c�N�a�j�@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�q�a�i�c�N�a�j�ƎO�d���@�@�N���b�N�Ŋg���@
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@��y�a�ƕ����r�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Q���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Ε��Q�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�Ε��@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k�擹��ɂāi�W���j�@�@�^���@�P���ƌ؎R�L�ˎ��@�����̋��{���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@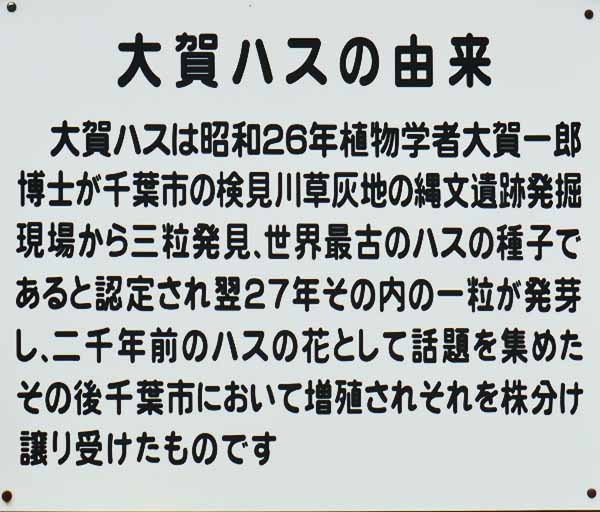
�_�ˎs�k�擹��L�ˎ��ɂāi�W���j�@���n�X�@�n�X�ȁ@�n�X���@�@�N���b�N�Ŋg��
�_�ˎs
�_�ˎs�k��
�����@
�����R�ϐ���
���̃y�[�W�̖ڎ���

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����R��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@  �@
�@ 
�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs�k���ϐ����ɂāi�W���j�@���ω���F���Ɣ����ω���F���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ 
�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����{���@���O�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs�k�扖�c�ɂāi�W���j�@�ϐ����O�̓c�����i�@�L�n�Z�b�R��]�ށ@�N���b�N�Ŋg��
�O�c�s
�O�c�s�K��
�����@
���v�R�ӏ���
���̃y�[�W�̖ڎ���
����炭��痋����̎�
��1000�N�O�A���a�����������̊J��ɂ��^���@����ŌK���R�ӏƉ]���Ù��ł������B
���̌�A����Q�N�i1228�j�����T�t�����w����߂�A�L�n����łۗ̕{�̍ہA�K���ɗ�����������A
���̎��̎R���v�̕s�V�R�Ɏ��Ă����̂ő��v�R�ӏ����Ɩ������A�����@�ɉ��@���ꂽ�B�����ɂ͗��̎q����
�������`���̈�˂�����A���݁A������̂����Ƃ��ĐM�҂������B�i ����痋�����̓`���@�j

�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ 
�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��e�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@  �@
�@ 
�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��ƍ����̐Ε�����ѕ�ΌQ�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�O�c�s�K���ɂāi�W���j�@�ӏ����@�R��̉��̖{���i���C���j�@�@�N���b�N�Ŋg��
������
�P�H�s
�V��@�ʊi�{�R
���ʎR ������
���̃y�[�W�̖ڎ���
���̔�b�R �����O�\�O�ԎD��
�V��̎O�哹��Ə̂��ꂽ����
���̔�b�R�Ƃ���قǎ��i�͍����A�����O�\�O�ԎD�����ő�K�͂̎��@�B
��b�R�A��R�ƂƂ��ɓV��̎O�哹��ƕ��я̂��ꂽ�����ł���B���s���牓��
�y�n���ł��邪�A�c����M���̐M���Ă��A�K���V�c��@�c�����������B
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�m���� |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@���߂̏��@ |
|
���Ɍ��P�H�s���P�H���̐��k��6�q�� �@�N��3�N�i966�j�����l�ɂ���ĊJ���ꂽ�A |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��������ف@ |
 �P�H�s�����R�������ɂāi2���j��u���@�����H�� |
 �P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�m����@���� |
 �@
�@
�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�\���@�@
 �@
�@
�P�H�s�����R�������ɂāi2���j����a
 �@
�@
�@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@����a����@�@
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j���[�v�E�F�C�R���w �����ɐ��˓��C��W�]����A�R�[�w�͖��O��̑O�ɂ��� |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j���ʐH���@�E��u���@ ���ɏ�s���@�����ɐH���@�E�ɑ�u���ƃR�̎��ɔz�u |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j������ |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�Q�� |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@�@�ؓ��@ |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@����a���䂩��{�V�@ |
 �@
�@ 
�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�P�H���{���ƕ_��
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j��ʉ@�@ |
 �P�H�s�����R�������ɂāi2���j��s���@�E���H�� |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��s���@ |
 �@�P�H�s�����R�������ɂāi2���j�@��u���@ |
�^���@
�����s
����R�^���@
����R������
���̃y�[�W�̖ڎ����@
����̖{�� �d���̏��O��L����翂̌Ù�
�@����l���J�������ƌ���
�V��������̉_�ɏ�����n�������@����l�������R�ɊJ��������
�`�������B�{���͂Q�̂̏\��ʐ����ϐ�����F�����ł���B���̂����̂P�̂�
���s�O�\�O�ԓ�����̂��Ƃ������Ă���B
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������R�� |
 ���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������@�{���i����j |
 �@
�@
�@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������@�@�@�E�����������O�i�d���j
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������� |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�������R��m�� |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@ ���������s���� |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j �@�����������g�ˉ@ |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������g�ˉ@ |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@�����������g�ˉ@ |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@���������������@�@ |
 �@���Ɍ������s�ɂāi11���j�@���������������@ |
�V��@
�����s
�V��@
��ԎR������
���̃y�[�W�̖ڎ���
�V���������@�����n���ƌ���
�@���`�ł�1,800�N�O�A�V���������@�����n�������Ƃ����B
���ÓV�c35�N�i627�j �����ÓV�c�����{�����������B����ɐ_�T2�N�i725�j
�����V�c���s��ɖ����ču�������������Ɠ`����B�@������25�ԎD��

���Ɍ������s ������25�ԎD����ԎR�������ɂāi11���j�@�m����
 �@
�@
���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��u��

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��u��
 �@
�@
���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�{�V���@�@�E�͖{�V�q�a

���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j����
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@���{���� |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�n���� |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@ �n���� |
 ���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j �������ւ̗��t�� |
 ���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j�@�� |
 ���Ɍ������s��ԎR�������ɂāi11���j�@ |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@������ |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�����O�̂��݂� |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@��t�� |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@���O |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@�哃�Ղ� |
 ���Ɍ������s ��ԎR�������ɂāi11���j�@������ |
 �@
�@
���Ɍ������s ������25�ԎD���@��ԎR�������ɂāi11���j�@����
�E�͐��������X�ɂāi�P�P���j�@�C���V�l�@�q���� �@�}���o�r����
����R
�_�ˎs
����R�^���@
�ŕꖀ��R�V�㎛
���̃y�[�W�̖ڎ���
��C������莝���A�������̖��둜�����u
�Z�b����R�̈���ƂȂ������@
 ��ɋ�C������莝���A�������̖��둜�� �����Ɉ��u������R�V�㎛�ƂȂ��� |
 ����R�V�㎛�{���@���ꖀ��R�V�㎛ �F���V�c����ɂ��C���h�̍��m�@����l���J�n |
 ����R�V�㎛�{���@����R�V�㎛�@�����̋��i�E�j�@�u��襉̔�̃y�[�W�v�� �^�Ӗ앓����1716�`1784���@�u�̉Ԃ�@���͓��Ɂ@���͐����v |
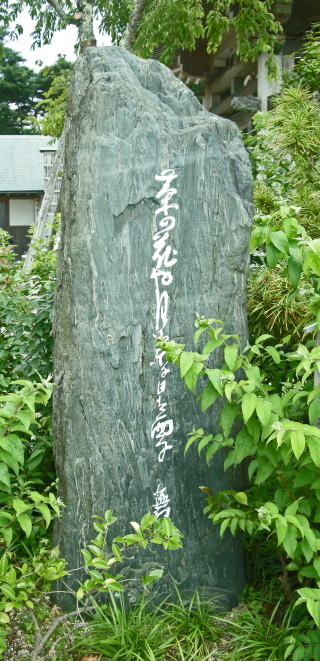 �^�Ӗ앓����� ����R�@�V�㎛�ɂ� |
 ����R�V�㎛�@�ʐ^�N���b�N�ŗ��ē��g�� |
 �@ �@ �F���V�c����̖���R�V�㎛ �ڂ̑傫�ȁu���߂ł�������v�Ɓu�Ⴉ����v������ ���Y�A�����ɂ����v������Ƃ��� ���̎�����̒��]�́u���R�̕��i�̃y�[�W�v�� ���̎��̋�襉̔�́u���̔�̃y�[�W�v�� |

����V�㎛�ɂāi�V���j�@�����̖̉ԁ@�Ē�
�����o���Ƃ��Ă�邪�C���h�̎߉ނ䂩��̍����o���ƈقȂ�
���ɋ�
�_�ˎs���ɋ�
�V��@
��ώR�\����
(�\���썑����)
���̃y�[�W�̖ڎ���
������(�ʖ�������)���̋F�莛�B���s�@�@��Ղ̋��@�ƁB
�{�a�͋��s��O���̌���˂��ڒz�B���ɑ啧�Œm����B�n��1200�N�̌Ù�
����24�N(805)�ɍŐ��ɂ��n�����ꂽ�A���{���̖����������ł���B��ɕ����������̎��Ƃ��āA����4�N(1180)��
���ƈ��̋F�莛�ɒ�߂�ꂽ�B���i�͍����A�c���̖�Ղ�{�炷�鋞�s�@�@��Ղ̉@�Ƃł������B�{�a�͋��s��O����
���(�����)����A���a28�N(1953)�Ɉڒz���ꂽ�B����24�N(1891)�ɁA��𑑕��q�̊�i�ɂ��啧���������ꂽ�B
�펞���ɍ��ɋ��o�����܂œ��{�O��啧�̈�ɐ�����ꂽ�B���݂̑啧�͕���3�N(1991)�ɍČ����ꂽ���́B

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@�啧�@���I�ɓߕ��i�����ՏƁj
�啧�̊ďC�͓����|�p��w���_�����@�����������@�ʐ^�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@�{���@���։e�a�i���̂킦���ł�j�v�@�ʐ^�N���b�N�Ŋg��
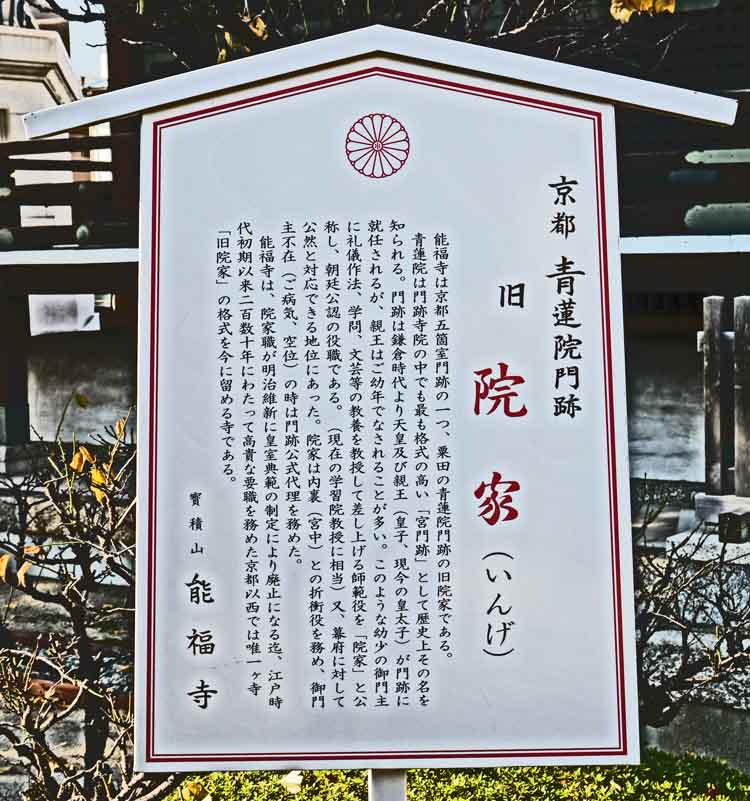 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@�V��@��ώR�\�����@������@�Ɛ����@�@�{���@�Ő��`����t�c�`��
�S�ăN���b�N�Ŋg�債�����͓ǂ߂܂�
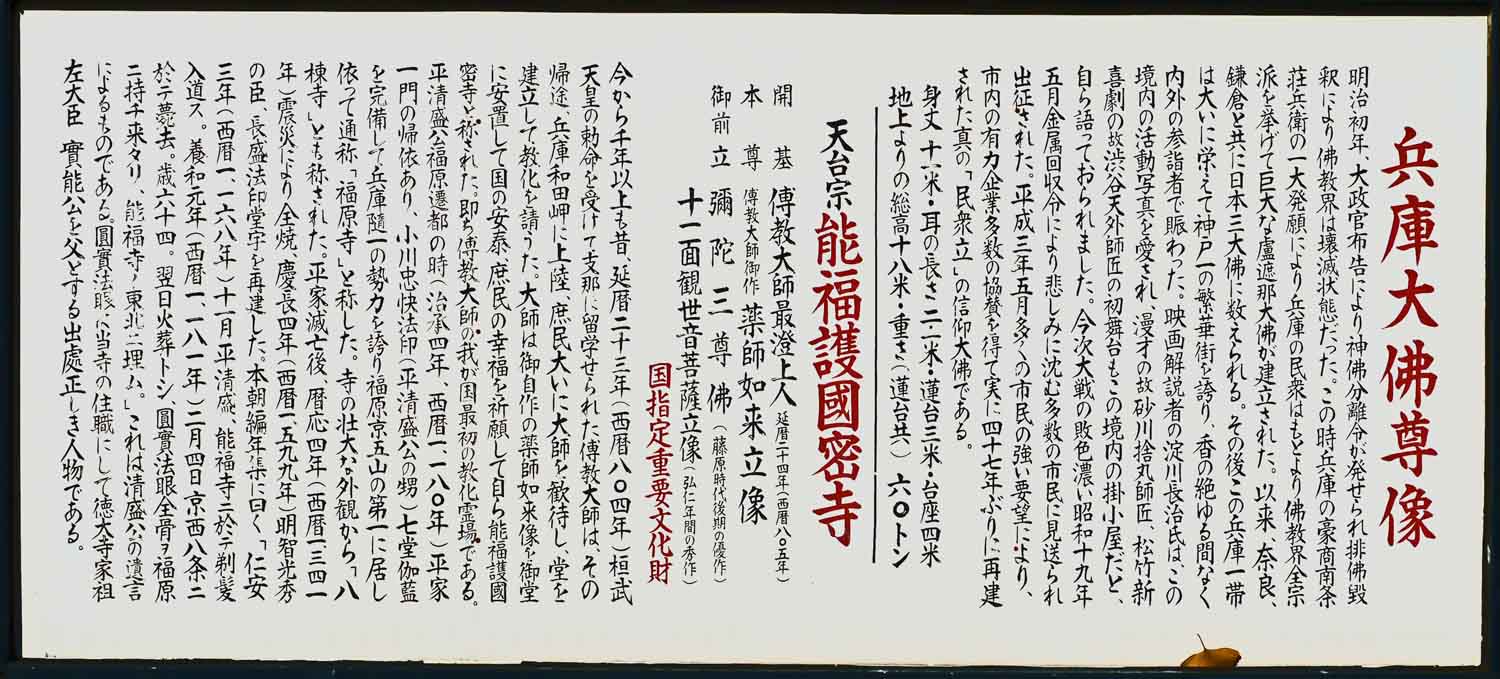 �@
�@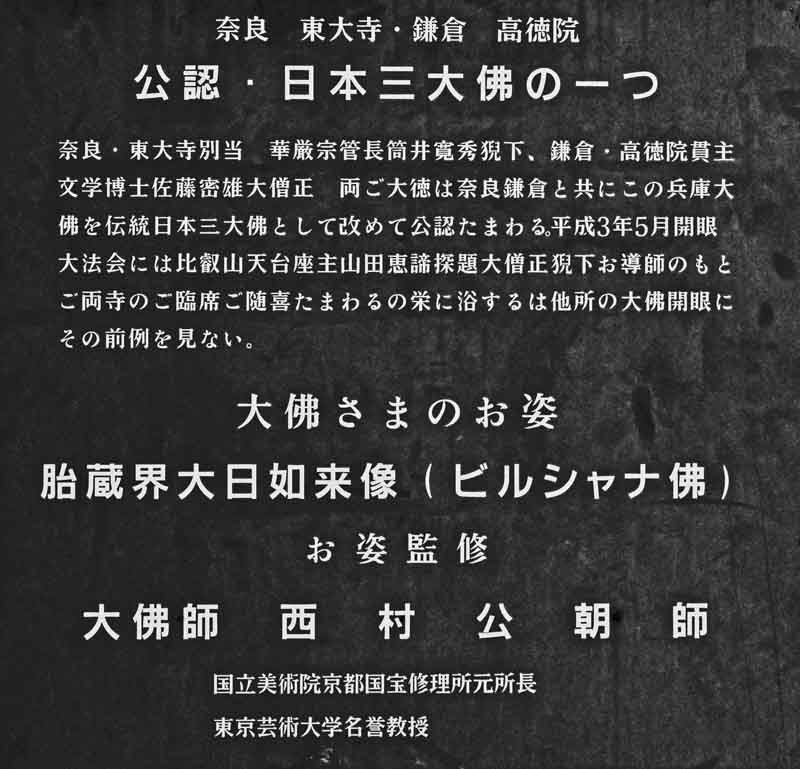
�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@���@�A���ɑ啧�����@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@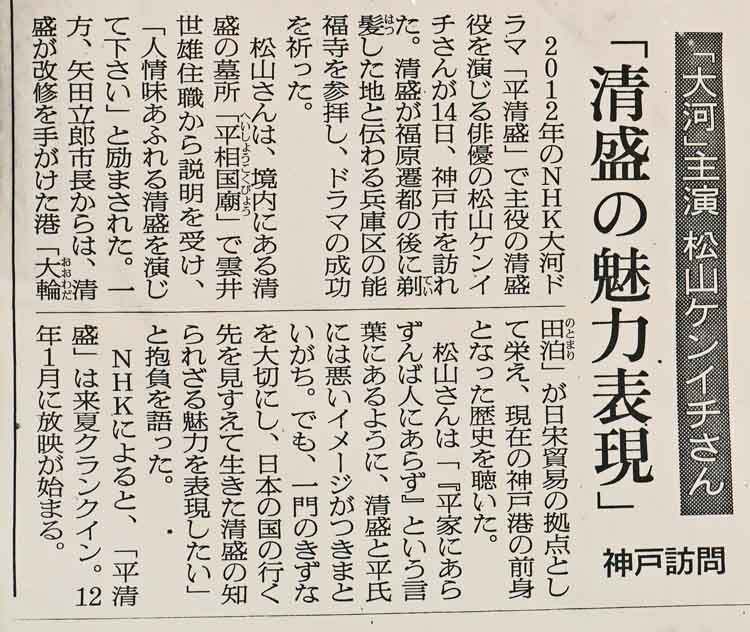
�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�������_�@���R���������揈�@�@�@�N���b�N�Ŋg��
�E�[�̐V���L����NHK�̘A���h���}�Ŏ���̏��R�P���C�`���\�����������_��K�ꂽ�Ƃ�������
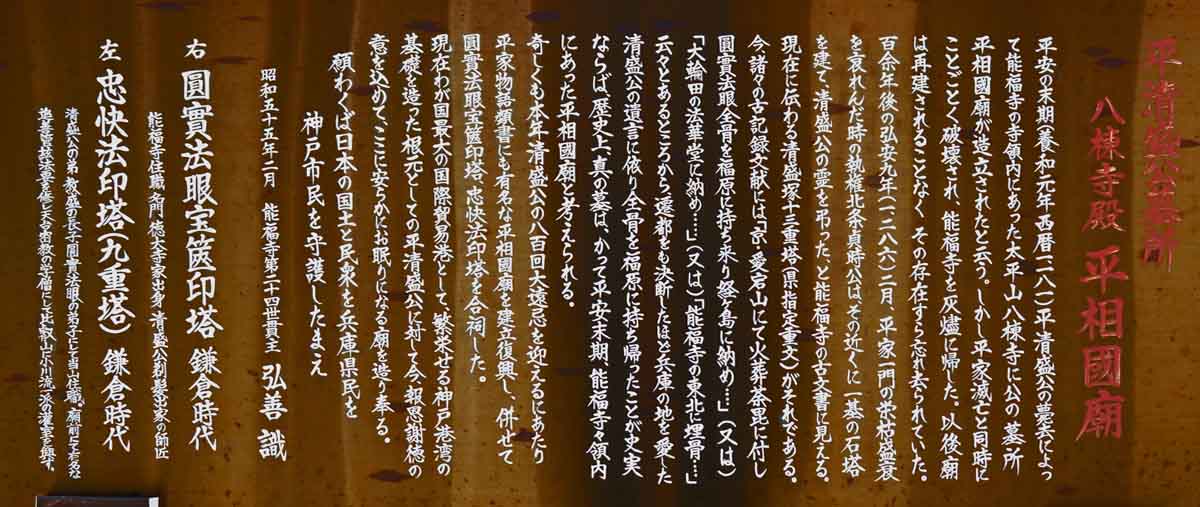 �@
�@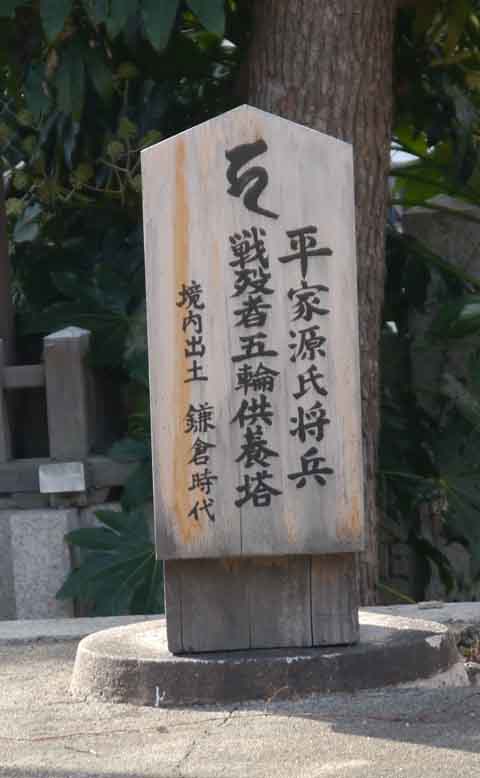
�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�������_�@�����@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�_�ˎs���ɋ�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@������{�V�@�뉀�@�u���@�@�N���b�N�Ŋg��
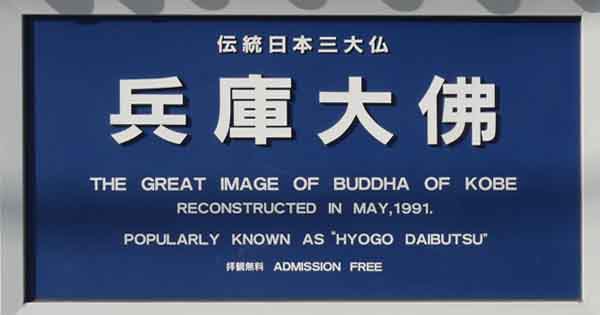 �@
�@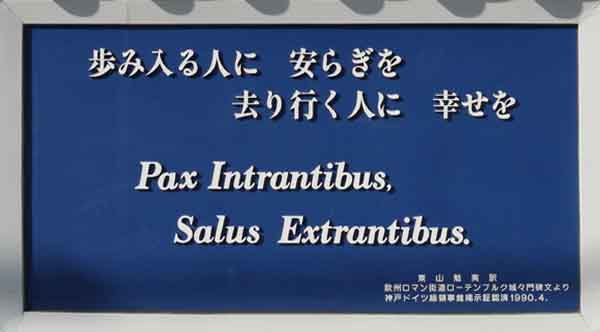 �@
�@
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@��N�n��1200�O���}�����Ù��\�����̎����O��@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@���O���݂�҂���т鞐���i���ʂƑ��ʁj
���ɂ́u�얳���I�Փߔ@���v�@�u���a40�N�X���Ē��v�ƍ��܂�Ă���@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ �@
�@
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�����̕����Q�@�@�N���b�N�Ŋg��
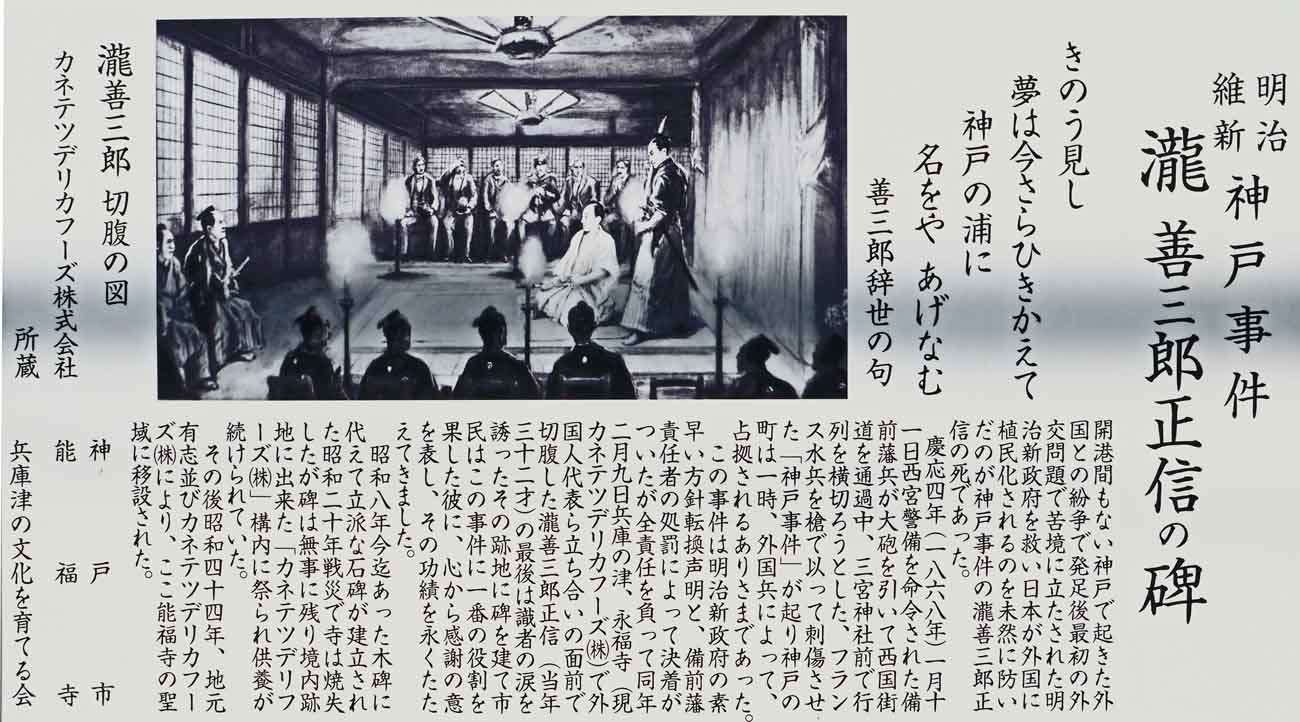 �@
�@ 
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�����ېV�ɋN������P�O�Y�Ɋւ��_�ˎ����̔�@�@�N���b�N�Ő������g��
 �@
�@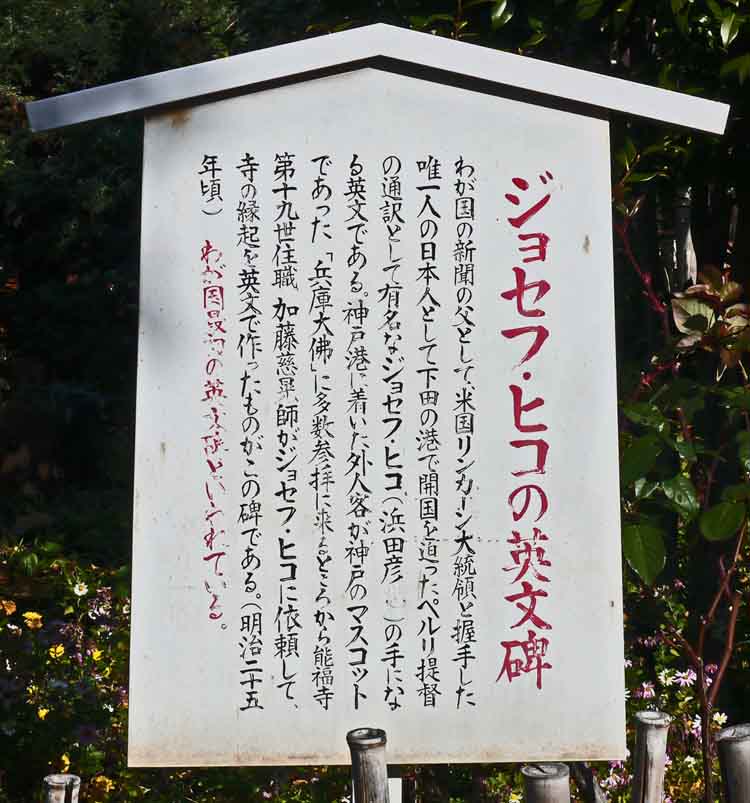
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��
 �@
�@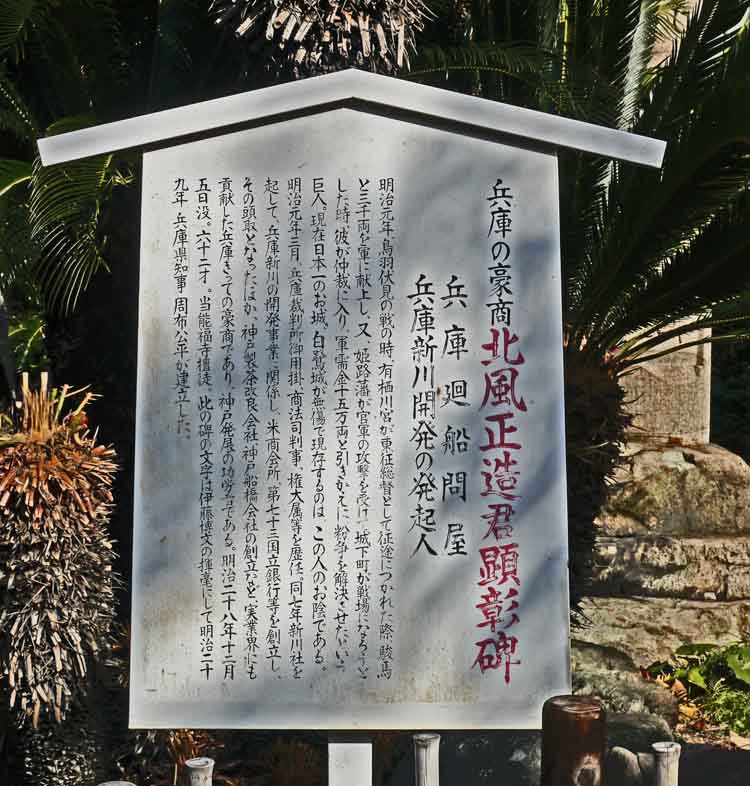
�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��
 �@
�@ �@
�@�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�N���b�N�Ő������g��
 �@
�@
�_�ˎs�V��@��ώR�\�����ɂāi12���j�@�@�ʐ^���@�~�̙֎썹���@�����ȁ@�q�K���o�i���@
�ʐ^�E�@�}���~�̎��@�j�V�L�M�ȁ@�j�V�L�M���@�N���b�N�Ŋg��
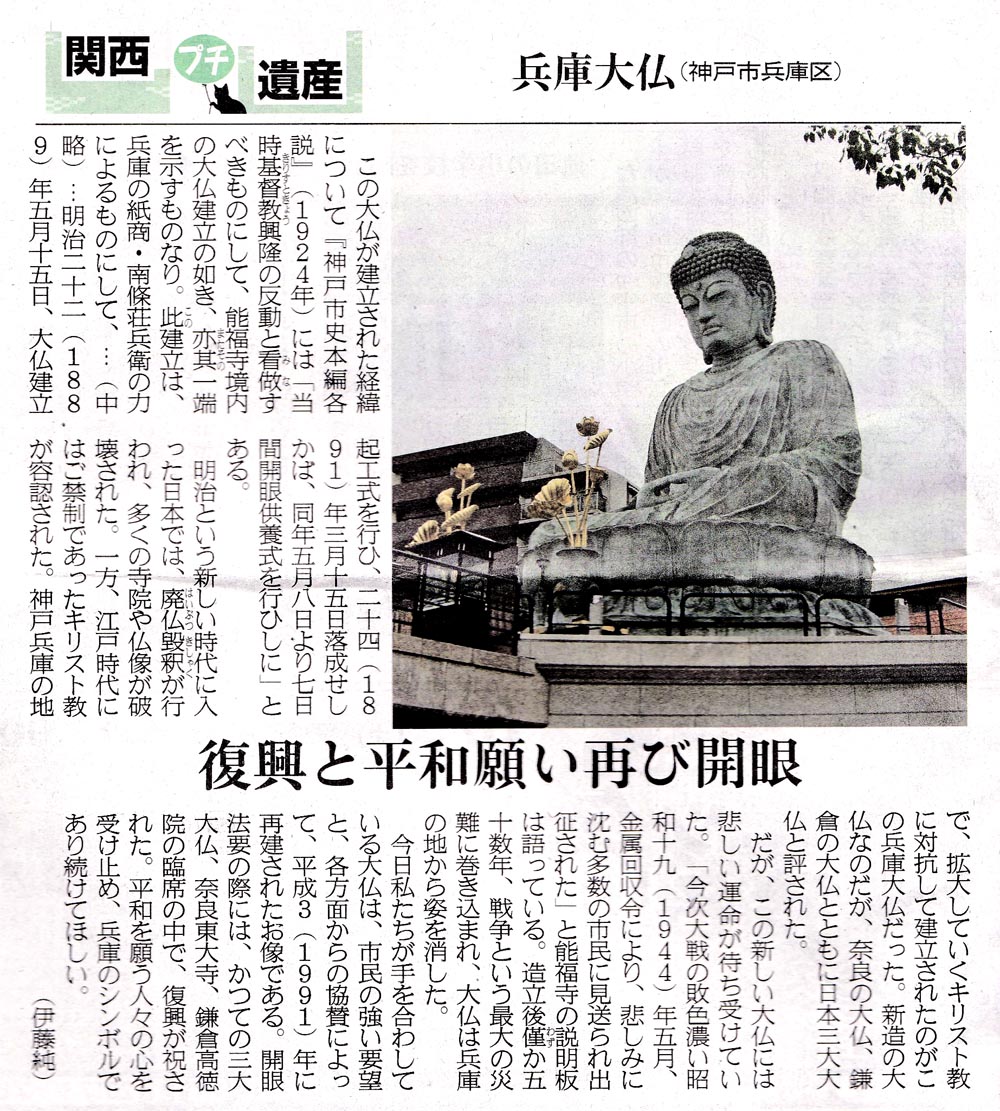
����29�N7��22���@�������@�N���b�N�Ŋg��
���@
�_�ˎs���ɋ�
���@
�����R�^����
���̃y�[�W�̖ڎ���
��Տ�l��_�̂��鎛�@
�m���V�c�i833�N�`850�N�j�̂���A�b�ӂ������ϐ����������A��A�a�c���őD�������Ȃ��Ȃ�A�������Ă�
�J�����̂��n�܂�B����2�N�i1276�j��Տ�l�����̊ω����ɏZ���Ē����J�c�ƂȂ�B��Տ�l���@�c�Ƃ���
����s�̎��@���{�R��������i�V�s���j�̖����B��̑��̋�P�Ŏ���̑唼�����������B�@�@�@

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�{���@�@�@�N���b�N�Ŗ{���������g��
 �@
�@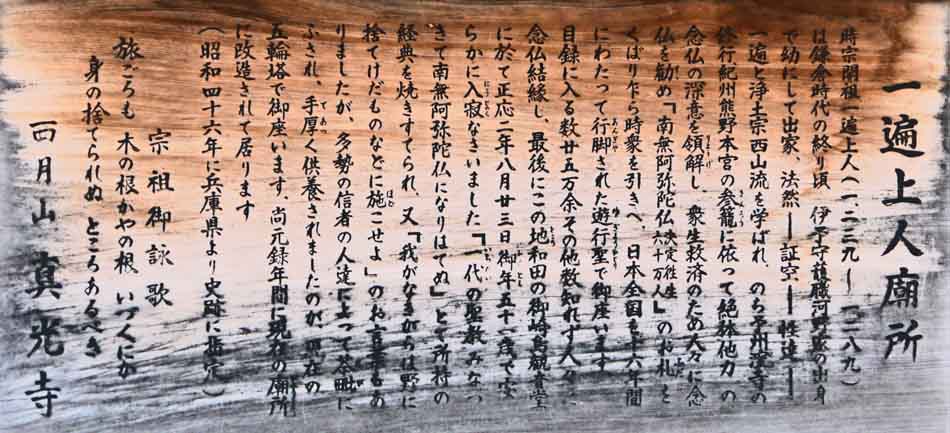
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����̑c��Տ�l�_�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@  �@
�@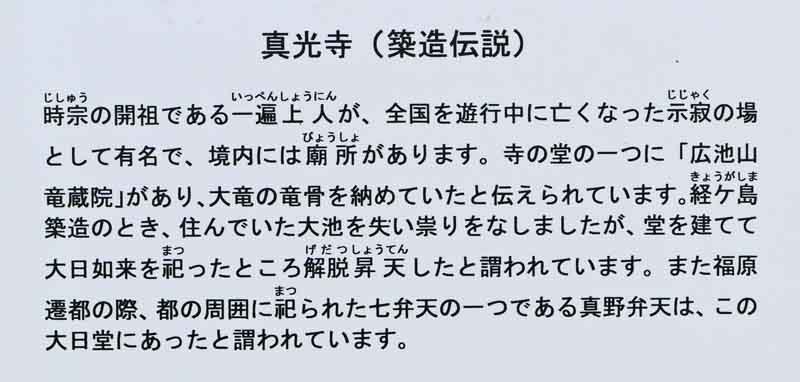 �@
�@�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����̑c��Տ�l�_�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@����������@���ɎR��@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�����k�����@���ɖ{���@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�����a�Ə��O�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@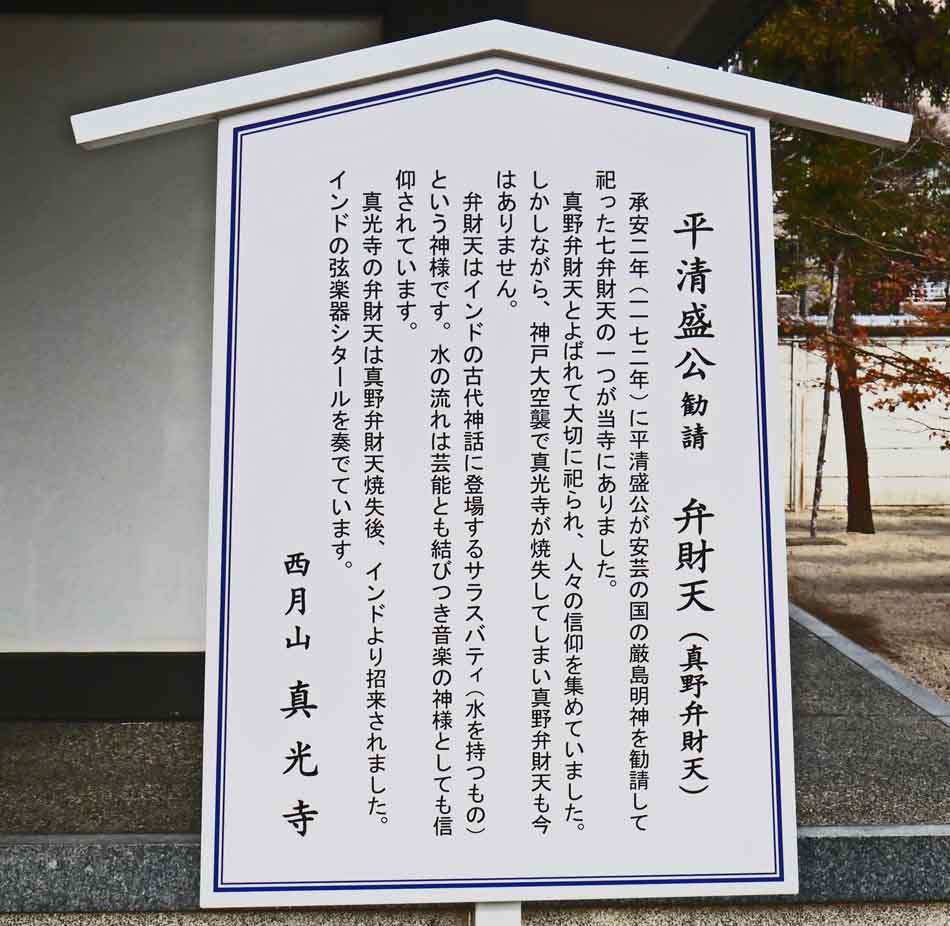 �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�ω����@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ 
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�ω����@�ω����̓������a�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�@�{�����뉀�@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@ 
���ɋ�ɂāi12���j�@���@�����R�^�����@�R��Ɓu��h�сv��@�@�N���b�N�Ŋg���@�@�h�тƂ��m���{���@��
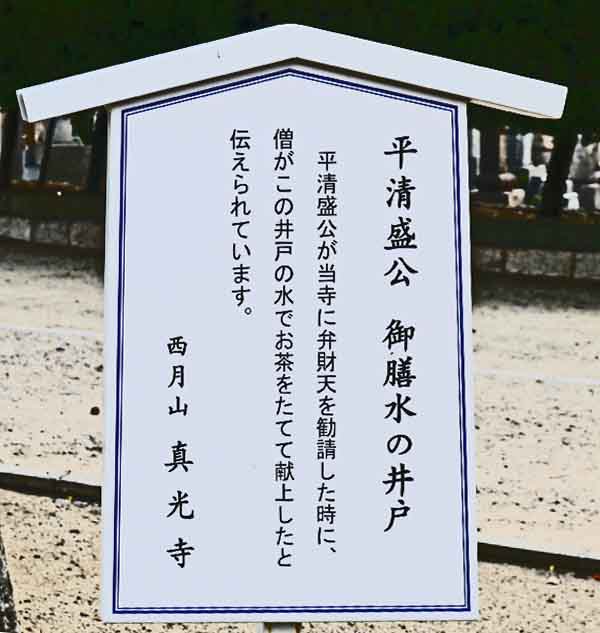 �@
�@
�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�������@��V���̈�ˁ@�N���b�N�Ő����g��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�F�쌠���ЂƖ����@�����@�@�@�N���b�N�Ŋg��

�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�u�V�s���i�䂬�傤��Ȃ��j�v
�w�ȁu�V�s���v�ł́A�V�s��l(��Տ�l)�����B�s�r�̍ۂɁA�V�l�̎p���������̐��ɏo����Đ��s���r�u���̖��v��
�ē�����A�V�l�́A��l�ɔO�����������Đ������邪�A��ɂȂ��čĂь����A��l�ɖ��ɂ܂��̎��������
��ӂ̕��������Ďp�������A�Ƃ������ؗ��ĂɂȂ��Ă���B�@�Q�l�l�b�g���
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�������@�@�E�͐^���������ē��}�i�N���b�N�Ŋg���j
 �@
�@  �@
�@ 
�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@�Z�n���Ȃǂ̒n�����Q�@�E�[�͍g�t�U�N���̎��@�U�N���ȁ@�U�N�����@�@�N���b�N�Ŋg��
 �@
�@
�_�ˎs���ɋ掞�@�����R�^�����ɂāi12���j�@���@�@�N���b�N�Ŋg��
�͖�É_�i�����́@���傤����j���P�W�W�V�`�P�X�S�V���@�z�g�g�M�X���l�A
���q�剺�̎��@�o�m�@�u���I��i�v�ɐ��̌�Ղ��v
�]���؎R�i�����Â��@������j���P�W�X�V�`�P�X�V�R���@�o���l�\�
�@���@�@�w�тɓ��藾�ĉ͖�É_�ɔo����K���B
�^�������Z�E�@�u�e���Ă����̑c�_���v
���@�@
�_�ˎs���ɋ�
���@�@
�����R�@�@��
���̃y�[�W�̖ڎ���
���ˌ����̂䂩��̂���
���i���N(1394)�A�J����Z��l�̖����������đn�����Ƃ��A���ɂ̖������̒ʏ̂Œm����B
�]�ˎ���ɂ͓����O�Ƃ̎��Ƃ��ė���������߂��B���s�R�Ȃ̑�{�R�{�����M�������Ƃ���Ă���B

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�@�����R�@�@���@�@�t�߂̎ʐ^�@�@�\�����ƌ����������Ă���

�_�ˎs���ɋ�ɂāi12���j�@���@�@�����R�@�@���@
���ˎ�
�_�ˎs
�^���@�{�����h��{�R
���R���ˎ�
(�{����)
���̃y�[�W�̖ڎ���
��������̎j��
���t���a�c�����ň����グ�����ω�����m�a2�N�i886�j�ɕ�����l��
���̒n�Ɉڂ����̂��n�܂�B�����∤�̐t�̓J��ٌc�̏��A����ˁA
�`�o���|�̏��ȂǁA�����̏d���j�Ղ����݂��� �B
 �@
�@
�_�ˎs���R�{�����@�Q�����m�����@�{���������ē��}

�_�ˎs���R�{�����@�{�����{��
�{�����������N�i�����j�ɂ��Θa�c���C�����o���������ϐ�����F�����u���邽�߁A�~�a�V�c�̒����ŁA���Ɍ�
�w�R�b��R�k�������B��Ɍ��l�V�c�̒����ɂ��J�c������l�{�����R���ˎ������Ė{���Ƃ����J��B
 �{�����{���ւ̐Βi |
 �{���Ɍ������č����@����˕��ʂ�]�� |
 �{�����@������̒r |
 �����揊�i��ˁj�@ |
 |
 �{�����@���O�@�@�ٌc�̏��i�����j�@ ��̒J�̍���̍ہA�ٌc�����{�����璷���̐�� �|���ĒS���ŗ��w���Ƃ����B�����͕قɔ[�߁A ���̏��͈�̒J���픪�S�N�L�O�ɕ������ꂽ���́B�@ |
 �@�@
�@�@
�{�����@�O�d��
 �{�����萅�ɁE�܌ؐ����O�@�� |
 �z����̓��q�u����ۂ���v�̑��@�ʐ^�N���b�N�Ő����g�� |
 �u�Ԃ�������v �؋��ɍ������Ƃ������ �@�@�@ |
 ���ΐl�`���@�̖ؓ����Y�����{���̏����W�߁A ���R�̑��^�𗘗p���č��グ���Ɠ��̏��ΐl�` �ʐ^�N���b�N�ʼn���� |
 ���S�N�O�̕����E�F�J�����̈�R�����̏�� �\�Z�̕�������̒J�̕l�ӂɂ����āA �����̕����F�J�����ɓ����ꂽ�i���ƕ���j �u�J�̉��ɔg����肭��{���̏H�v�̕�����肪���� |
 ���Ɍ��@�^���@���R�{�����@���q���i��O���j�@ �t�̓J�̉� |
������
�_�ˎs
��y�^�@
�ˉˎR������
���̃y�[�W�̖ڎ���
��������ɏo�Ă��鎛�@
���������g�����Ƃ����
 ���Ɍ��{���@�ˉˎR�������{�� |
 �@ �@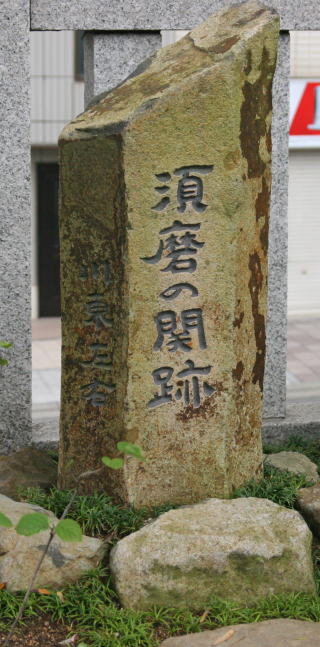 �����m�Ԃ����܂����Ƃ���錻���������� �E�͌����������ɂ���{���̐ȐՂ������Â��ΕW |
 ���Ɍ��{���@���������O�@�k�Е������� |
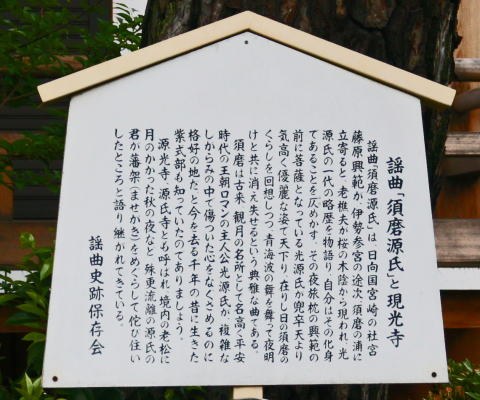 �������̐����@�@�N���b�N�Ŋg�� |
 ���������g�����Ƃ��� �������͌������Ƃ��Ă�� �P�O�O�O�N�ȏ�̗��j�����������A ��_��k�Ђœ|���z���ꂽ |
 ���Ɍ��{���@�ˉˎR�������{�� |